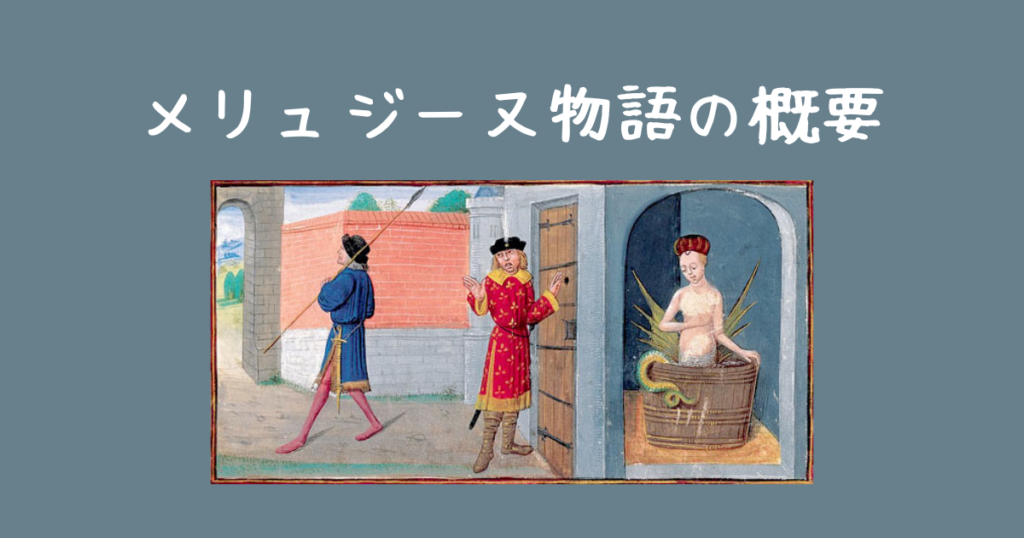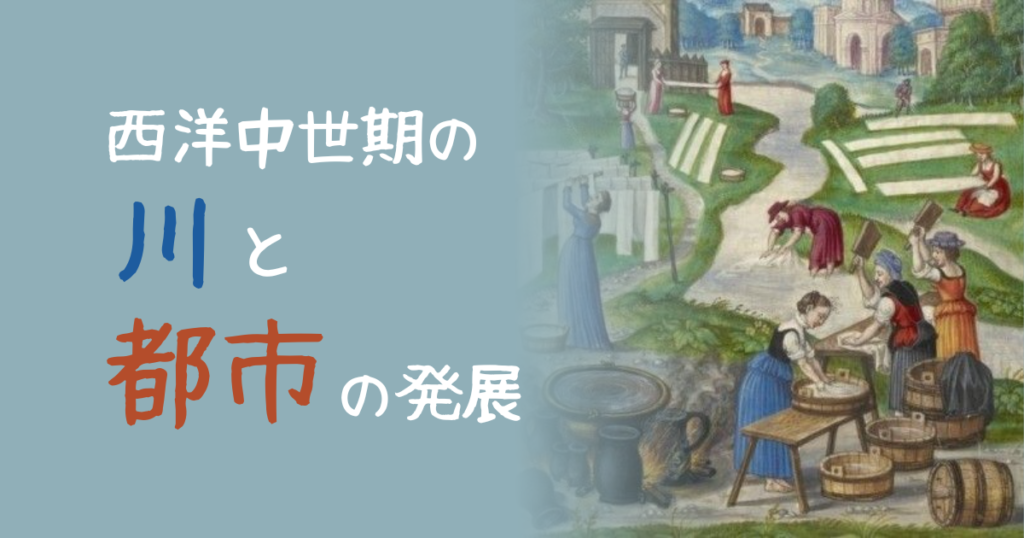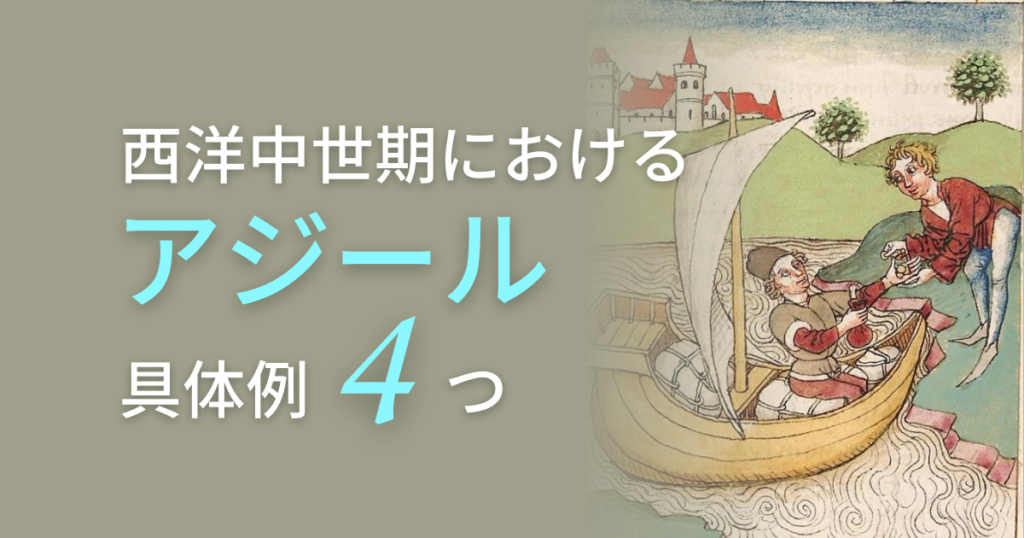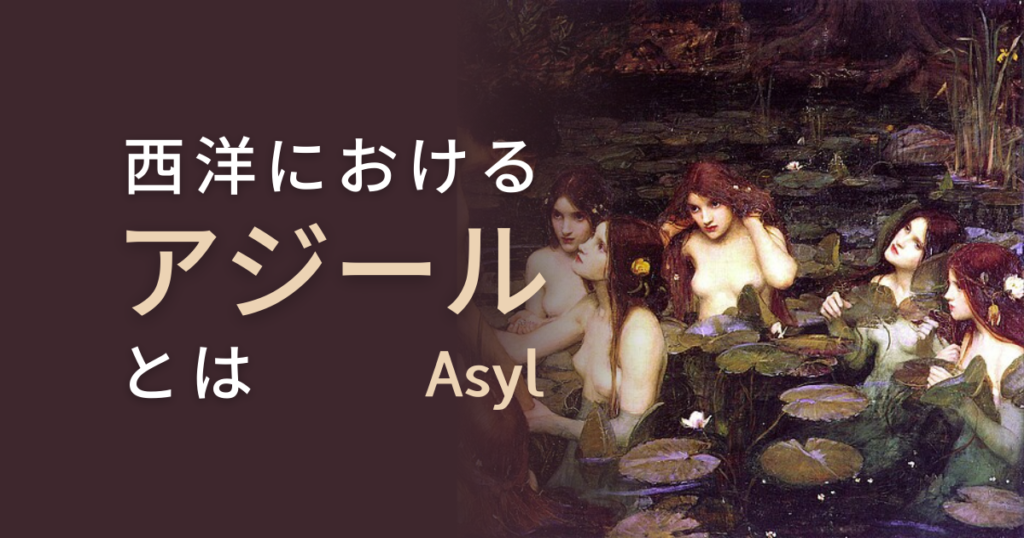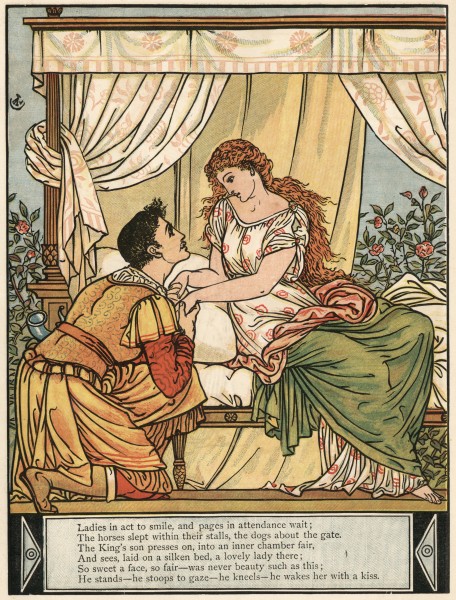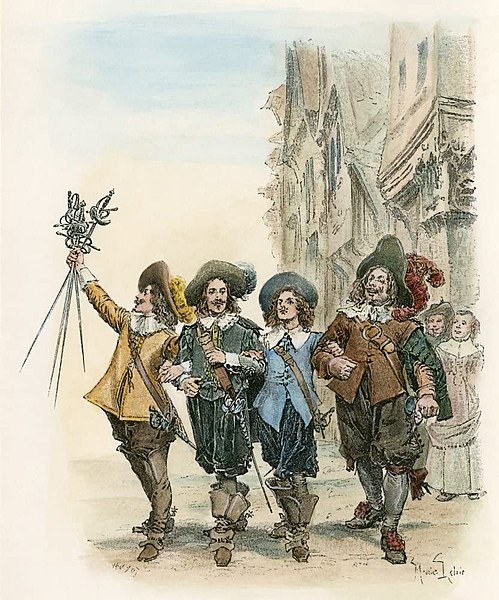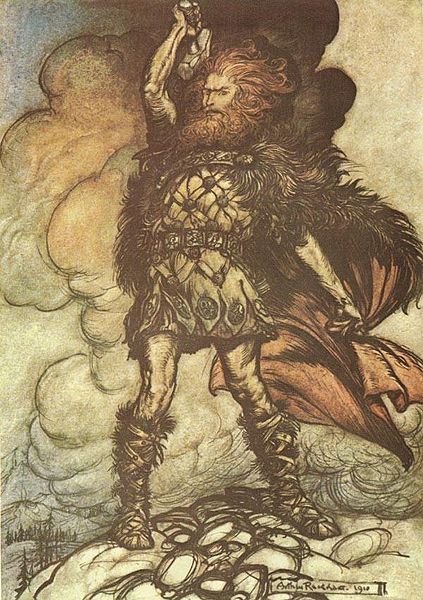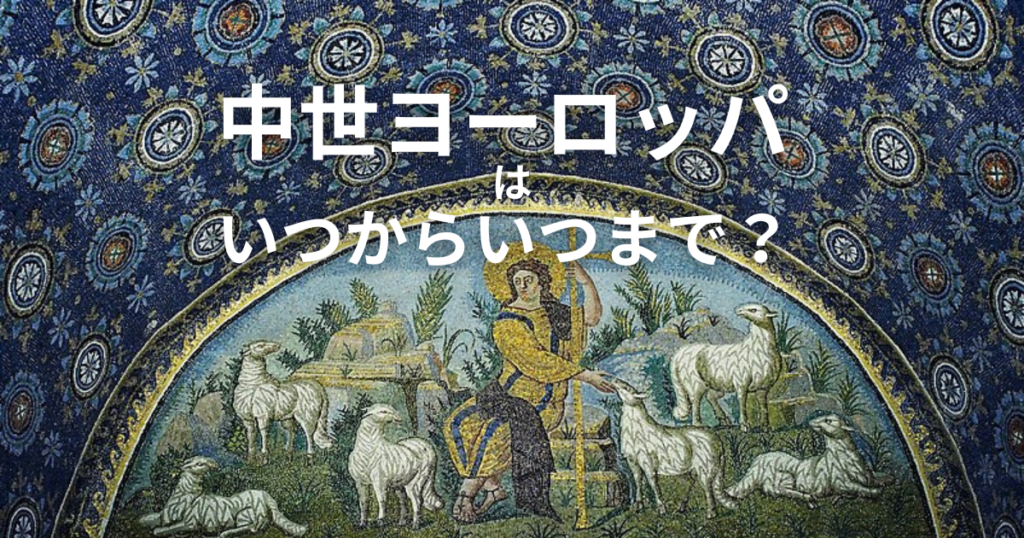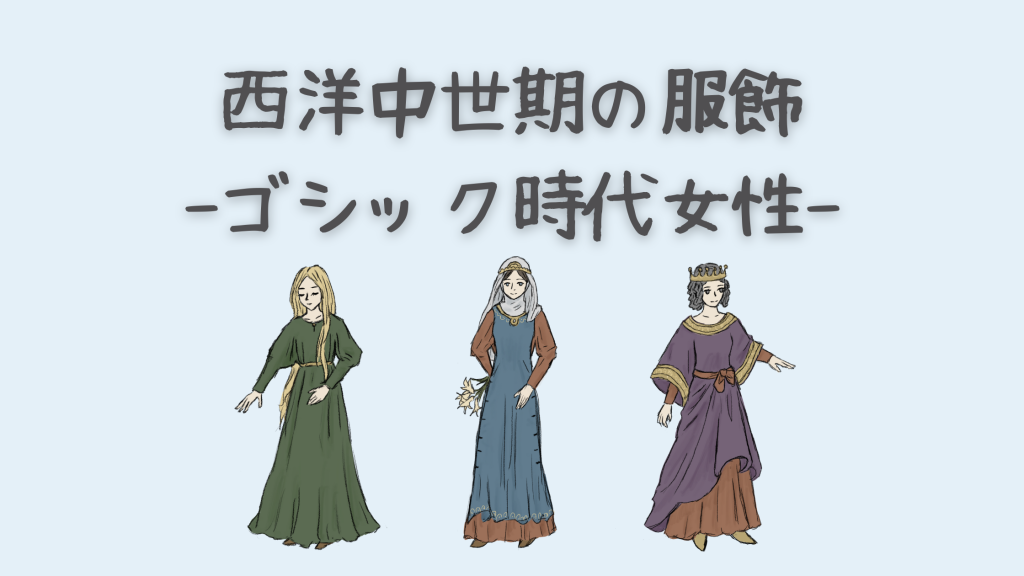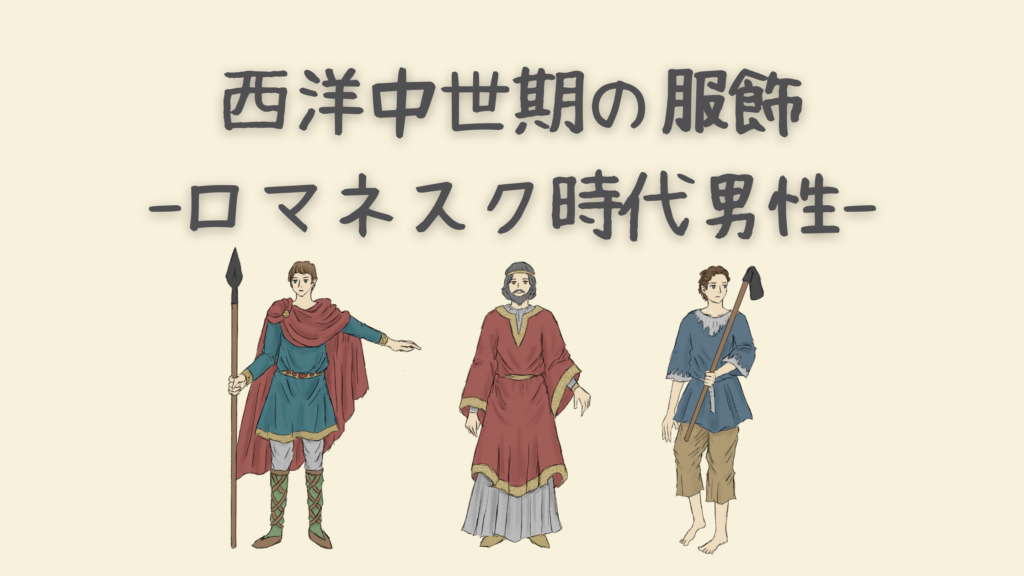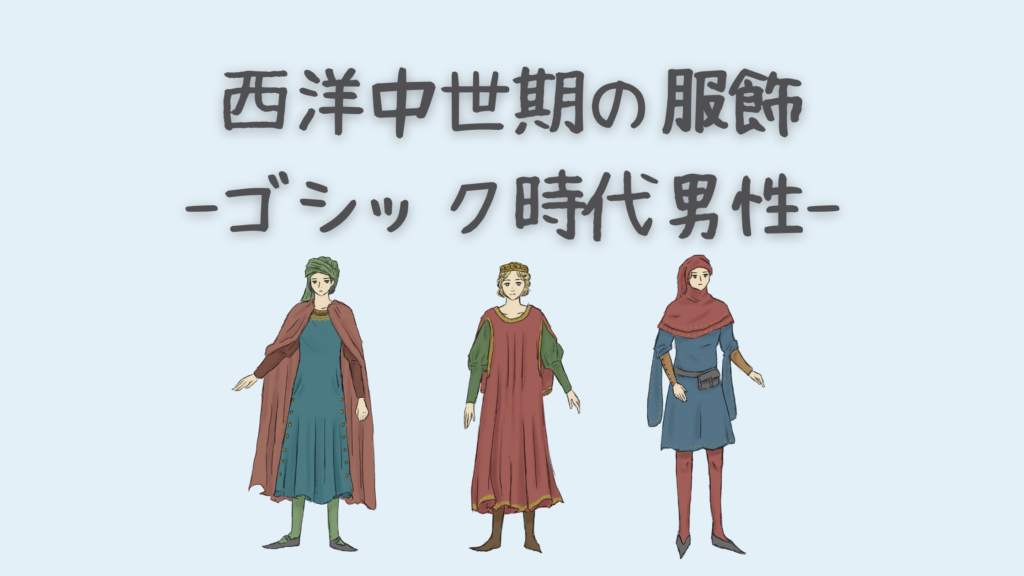投稿記事一覧
-

『メリュジーヌ物語』の概要
以下は、中世期の騎士道物語の1つである『メリュジーヌ物語』の概要です。騎士は湖で美女に出会うの記事で取り上げています。物語の舞台は現在のフランスです。 ポワエィエ伯エムリの従兄弟フォレ伯の三男であったレイモンダンは、エムリと共に狩りにでた... -

騎士は湖で美女に出会う
西洋中世期の騎士道物語において、主人公は森を冒険すれば必ず、湖(泉)で恋人となる女性に出会います。そこで出会う女性は、決まって美しく、キリスト教から見て「異教」的な存在、つまり妖精などの超自然的な存在です。 今回は、西洋の騎士道物語に登場... -

西洋中世期の川と都市の発展
中世ヨーロッパの都市は、川の恵みを享受しながら発展しました。今回は、都市の発展に寄与した川の機能を3つ紹介します。 川が人にもたらす恵み 人類の文明発展の礎となった四大文明は、川を中心として発展しました。四大文明とは、メソポタミア文明、エジ... -

ノマド(nomad)の語源
はじめに ノマドとは、英語のnomadまたは仏語のnomade(遊牧民)に由来しており、「ノマドワーカー」の略語です。ノマドワーカーとは、オフィスなど、特定の場所にとらわれずに働く人のことです。自宅だったり、河原だったり、山奥だったり、ネット環境さ... -

西洋における道の文化史
中世ヨーロッパの道は、自分たちの共同体(村や町)から延びる異界への案内線でした。そこには超自然的な存在がはびこり、盗賊も出現しました。そのため、共同体から外れた道を歩くのは、中世の人びとにとっては命がけでした。 今回は、西洋における道の文... -

西洋中世期におけるアジール【具体例4つ】
アジールとは「聖域」を意味し、人の権力が及ばない領域を意味します。なぜならそこは、神々や霊的存在の支配領域だからです。そのため人間の定めた法を犯した者にとって、格好の避難場所となりました。 今回は西洋中世期に存在したアジールを4つ紹介しま... -

西洋におけるアジールとは【概要】
アジールとは「聖域」を意味し、人の権力が及ばない領域を意味します。なぜならそこは、神々や霊的存在の支配領域だからです。今回は西洋におけるアジールについて、概要を紹介します。 アジールとは ジャン=バティスト・カミーユ・コロー《冥界からエウ... -

喜劇にむなしさを感じる理由
はじめに 喜劇でも悲劇でもない小説にて、喜劇の要素も悲劇の要素も持つ物語は、どちらか一方の要素しか持たない物語より魅力的であると述べました。 わたしたちは幼少期には喜劇(ハッピーエンドの物語)を好みますが、成長するにつれて、悲劇の要素を含... -

喜劇と悲劇の側面をもつ小説
はじめに 神話学者のジョーゼフ・キャンベルは、あらゆるもの(生物・物質)は滅びゆくため、人は悲劇の物語に惹かれると述べます。つまりバットエンドを迎える物語です。しかし幼い子供は喜劇の物語を好みますし(「こうして王子様とお姫様は幸せに暮らし... -

作者との内輪話によって読書はより楽しくなる
はじめに 本を日常的に読んでいる方は、こんな経験があるかもしれません。同じ作者が書いた本でも、同じジャンルの本でもないのに、「この内容(表現)、他の本でも見たな……」。さらに驚かされるのは、遠い昔に読んだ本ではなく、直前に読んだ本の内容が、...