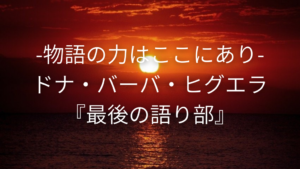はじめに
過去の記事で記載した通り、私はファンタジー愛好家だ。そもそも、小説を読む理由自体が、「自分の人生では経験したことがない、あるいは今後経験しないであろうことを経験したいから」なので、現実世界とは180度異なるファンタジー小説が嫌いなわけがない。大好きだ。
そういうわけで、普段は海外の古典文学ばかり読んでいる私だが、ファンタジージャンルだけは最新の情報を仕入れている。その最新情報を仕入れる一環として、2023年6月に発売された、多崎礼の『レーエンデ国物語』を読んだため、本記事でレビューを行いたい。ネタバレするので、そしてこの物語はネタバレすると楽しめなくなるタイプの物語なので、これから読もうとしている人は、本記事を読まないことをおすすめする。
なお、私が古典文学ばかり読む理由は「名作」が多いからだ。名作とは、ジョン・サザーランドによると、「人生で何が一番大切かについてのヒントを与えてくれる」小説だ(※人が小説を読む理由の引用を参照)。私が1年に読める小説は30冊程度なので、限られた人生のなかでできるだけ多くの「名作」を読みたいと思うと、自然と古典文学が中心になってしまう。
物語の概要
『レーエンデ国物語』は現時点では1巻のみ発売されているが、シリーズものになる予定だ。物語の大きな流れとしては、呪われた地として知られる「レーエンデ」という土地が、国として独立するまでの話になると予想される。第1巻で語られるのは、レーエンデが変革するきっかけとなった、のちに「レーエンデの聖母」と呼ばれることになるユリアと、ユリアを守り抜いたトリスタンという青年がたどった人生の物語だ。
ファンタジー要素
過去の記事、おとぎ話とファンタジーの違いにて、個人的なファンタジー物語の定義を記載している。ファンタジー物語とは、魔法などの超自然的な要素が出てくる物語だ。
この定義にあてはまると、『レーエンデ国物語』に出てくる超自然的要素は、レーエンデという土地そのものだ。レーエンデが「呪われた地」と呼ばれるゆえんに、その土地のみに発生する銀呪病という病がある。銀呪病は、一度発症すれば必ず死に至る病で、発症した人は銀の鱗が徐々に身体中に広がり、身体が動かなくなって(内臓も機能しなくなり)死に至る。
レーエンデでは、満月の夜になると、時化と呼ばれる幻の海が空中に発生する。それは銀色の霧として目に見え、霧の中では半透明の幻魚が泳いでいる。この時化を浴びることが、銀呪病を発症する原因となる。そのため、レーエンデの人々は満月の夜は必ず室内にこもり、外へでない。そうすれば病の発症を防げるからだ。
幻の海が発生すること、銀呪病にり患した銀色の動植物たちがいること(人間以外は銀呪病で死なない)が、レーエンデにおける超自然的要素で、この物語のファンタジー要素となる部分だ。
個人的評価
総合して、けっこう気に入った。しかし再読するか?と訊かれたら再読はしない。つまり一過性のエンターテイメントとしては楽しめるが、時代を越えて語り継がれるファンタジーか?(たとえばトールキンの『指輪物語』やル=グウィンの『ゲド戦記』のように)と問われれば、そうではない。また、小説としての描写表現(※)においては、国内ファンタジー作家の上端菜穂子のほうが優れていると思う。
※ここでいう小説の描写表現とは、小説という芸術が得意とする表現方法を指す。小説が得意とするのは、登場人物の心理描写だ。そういう意味で、「」で囲われた会話文が多い小説より、「」で囲われた会話文が少ない小説のほうが、登場人物の心理描写に重きが置かれており、小説として「本格的」と言える。会話表現が得意な芸術は、映画かアニメか漫画だ。
気に入ったところ
- レーエンデという土地の、ファンタジーならではの世界観。ウル族が暮らす木の洞、幻の海、幻魚よけの鉄鈴、(おそらく銀呪病にかかって死去した者の魂と考えられる)泡虫など、現実世界にはないものがたくさん書かれていてわくわくする。
- 物語の展開がシリアスなところ。トリスタンが銀呪病であることが発覚したとき、「これは死ぬ前に治療法が分かって助かる展開だろう」と思ったが、容赦なく死んだので、ご都合主義ではなく本当にレーエンデの「革命の話」をしたいのだなと思った。革命には犠牲がつきものなので、この後の物語でも多くの人が死ぬだろう・・・。
気に入らなかったところ
- 本の冒頭で、人物イラストをつけているところ。経験上、こういう本は小説として「本格的」ではない。小説なら文章だけで勝負してほしい。ビジュアルをつけるということは、文章のみの戦いを放棄し、安っぽい現代受けマーケティングに屈したということだ。
- 会話文中の言葉遣いが、くだけすぎている。敵ポジションのガフという人の言葉遣いが、まるで現代SNSのようで吐き気がした(むしろそれを狙っているのかも)。また、ヘクトルが「キレた」と言う箇所があり、「え!?いま『キレた』って言った?」と動揺した。馴染みやすい言葉遣いにするのはいいけれど、さすがに「キレた」はない・・・本にそんな言葉を印刷しないでくれ・・・と思ってしまった。
- トリスタンがユリアを最初から受け入れすぎており、違和感があった。トリスタンは辛い人生経験を積んでいる。そんなときに現れたのが、自分の身を自分で守れない、父に頼りっぱなしな、貴族のお嬢様であるユリアだ。「なんでお前、レーエンデに来たん?こっちは毎日、生きるか死ぬかの生活してるんだよ。遊びできたなら帰れ」と普通だったら思うのではないか。そこをすっとばして、初対面から打ち解けているのが訳が分からない。しかも初対面から距離が近すぎて引いた。
- トリスタンお前、寡黙キャラじゃなかったのか。ぜんぜん喋るじゃん。会話が全体的に、漫画的なボケとツッコミで成り立っており、トリスタンがツッコミ役なので、めっちゃ喋る。寡黙設定はどこへ?
- ユリアの父、ヘクトルの万能感と人の良さが「ファンタジー」。こんな人は現実にいないので、架空のキャラクター感が強く、物語にうまく馴染めていない印象を受ける。
おわりに
今回は、多崎礼『レーエンデ国物語』のレビューを記載した。
いろいろ書いたが、ファンタジー愛好家にとって新作ファンタジー小説に抱く感情は、それがどんな物語であれ、生み出してくれてありがとう、だ。新しい世界の体験をさせてくれてありがとう。共有してくれてありがとう。大感謝。
今回、気に入った点として、物語の展開がシリアスなことを挙げたが、正直、シリアスすぎて辛かった。私にとって小説とは、明日を生きる活力をもたらしてくれるものであってほしいので、精神的にきついのはちょっと嫌だ。『レーエンデ国物語』は続くらしいが、続きを読むかはちょっと考えさせてほしい。
以上、『レーエンデ国物語』のレビューだった。