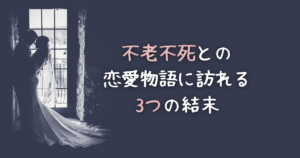人間による不老不死の希求や、不老不死の存在との恋愛は、太古から繰り返し語られてきた、人気の物語テーマです。本記事では「不老不死とはどのような状態なのか?」「人間にとって、不老不死になることは幸せなのか?」などを考察します。
不老不死について考えはじめたきっかけ
私が不老不死について深く考えはじめたのは、J.R.R.トールキンの『指輪物語』を読んだときでした。『指輪物語』には、不老不死で美しい容姿をもつことが特徴の、エルフという種族が登場します。
エルフとはもともと、北欧神話に登場する超自然的な存在です。しかし現代の私たちが「エルフ」と聞いてイメージする、細身で美しく尖った耳をもつエルフ像は、『指輪物語』およびそれを映画化した『ロード・オブ・ザ・リング』3部作によって植えつけられました。『指輪物語』のエルフ像は、昨今の漫画アニメを含むあらゆるファンタジー物語に影響を与えています。
エルフが不老不死であるのは、(今やどんなにその力が弱められたにせよ)彼らがもともと神の末席に位置し、神性を持っていたからです。『指輪物語』原文においては、エルフを形容する「永遠の命の」という意味でimmortalが、人間を形容する「限りある命の」という意味でmortalが使用されています。映画の1部作目、冒頭でのガラドリエルによる以下の台詞に聞き覚えのある方は多いことでしょう。
It began with the forging of the Great Rings.
それは指輪の誕生ではじまった。Three were given to the Elves, immortal, wisest…fairest of all beings.
3つの指輪がエルフのものに。不死の命をもつ、最も賢く美しい種族。Seven to the Dwarf Lords, great miners and craftsmen of the mountain halls.
7つの指輪はドワーフの族長へ。山の邸宅の、鉱石採掘と工芸に秀でた種族。And Nine…nine rings were gifted to the race of Men who, above all else, desire power.
そして9つの指輪は人間に贈られた。他の種族と異なり、権力を強く欲する種族。For within these rings was bound the strength and will to govern each race.
それらの指輪で各種族は自らを治める力と意志を得たはずだった。But they were all of them deceived…for another ring was made.
映画『ロード・オブ・ザ・リング 旅の仲間』冒頭より
しかし彼らは全員あざむかれた……というのも、もう1つの指輪がつくられていたから。
『指輪物語』では、人間であるアラゴルンと、エルフであるアルウェンによる、種族を越えた恋愛が物語を盛り上げる一要素となっています。アラゴルンは限りある命であるのに対し、アルウェンは永遠の命を持っています。つまり二人の恋の成就までには、寿命の違いという大きな障壁があり、その障壁が物語を盛り上げるのです。
『指輪物語』以降、人間とエルフ(あるいは妖精)による、寿命の違いという障壁を乗り越えた恋愛は、さまざまな作品で何度も焼き増しされてきました。最近の物語の例でいうと、漫画『葬送のフリーレン』では、”恋愛”ではなく”友愛”といったほうが適切だと思いますが、まさにこのテーマを扱っています。
私は『指輪物語』を読んだあとも、不老不死の存在が登場する物語にたくさん触れてきました。その過程で、不老不死とは何だろうか? 不老不死になることは本当に幸せなのだろうか? ということを考えてきたため、今回は不老不死をめぐる考察をしたいと思います。

人間は不老不死を希求する
人間は生まれてから現在に至るまでの成長過程で、これまでの人類の思想史を追体験する、そう私は考えています。
具体的には、ある年齢まで私たちは、前近代的な思考をしています。例えば「夜道はおばけがでそうで怖いから、一人で歩きたくない」「てるてる坊主を窓辺に吊り下げたから、明日はきっと晴れになる」といった思考です。しかしながら、成長するにつれて私たちは超自然的な力を疑うようになり、それに置き換わる「科学」という知識を手に入れます。そうして私たちは、世界は超自然的な力ではなく、科学によって支配されているという、現代的な思考をするようになるのです(※)。
※人類思想上の、世界を認知するためのベースの置き換わりは、魔法から科学への移行を参照。
そのように考えると、現代人の私たちでも、子供の頃を思い出せば、前近代の人の気持ちが分かるはずです。子供の頃の私たちは、いったい何がいちばん恐ろしかったのか? 多くの人が挙げるのは「死ぬこと」だと思います。なぜなら死後の世界は、生者である限り永遠に未知なるものだからです。「死んだら自分はどうなるんだろう?」ということを、多くの人が子供の頃に一度は真剣に考えたことがあるはずで、ときにはそれを大人に質問したことでしょう。
この永遠の旅路を人はただ歩み去るばかり、帰ってきて謎をあかしてくれる人はいない。
オマル・ハイヤーム『ルバイヤート』小川亮作訳、岩波文庫、1979年、44頁。
実は、その問いは大人になった今でも、解消されていません。なぜなら人間の意識が死後にどうなるかは、科学によっても解明されていないからです。ところが科学(医療)が発展した現代では、日常生活を送るなかで死ぬリスクが低いため、私たちは(健康なうちは)死の恐怖を考えずに済んでいるのです。
よって、前近代の人びとにとって最も恐ろしいことは、「死ぬこと」あるいは、死に近づくという意味で「老いること」でした。人びとはいつか自分に降りかかる死に怯え、不老不死になりたいと願います。その願いは、科学的思考によって可否を判断できない彼らにとっては、何とかすれば実現できそうに思えました。彼らの世界は超自然的な力が支配していたため、何かの拍子に――例えば秘密の妙薬を飲むことによって――不老不死になれてもよさそうでした。

人間による不老不死の希求は、たいへん古い時代からありました。例えば、約4000年前にメソポタミアにて成立した、世界最古の叙事詩『ギルガメシュ叙事詩』は、ウルクの王ギルガメシュによる、不死の追究がテーマになっています。ギルガメシュは、共に冒険を乗り越えてきた親友・エンキドゥが天罰により死ぬのを目の当たりにしました。彼は友の死を悼みながら、自分もいつか彼のように死ぬことを恐れました。
私が死ぬのも、エンキドゥのごとくではあるまいか
『ギルガメシュ叙事詩』第九の書板、一3-5、矢島文夫訳、ちくま学芸文庫、2024年
悲しみが私のうちに入り込んだ
死を恐れ、私は野原をさまよう
そこでギルガメシュは、不死になった賢者・ウトナピシュティムに、永遠の命を得る方法を尋ねることにしました。長く困難な旅のすえ、ギルガメシュはウトナピシュティムの元に辿りつきます。しかし、ウトナピシュティムからの回答は、「不死になることは人間である限り不可能」というものでした。
ウトナピシュティムは、かつて大洪水の際にエンキ神に生き残ることを選ばれた人間でした。その結果、妻とともに神々と同列に迎えられたため、彼はもはや人間ではなく神でした。ゆえに不死の属性を持っているのでした。そうしてギルガメシュは、永遠の命を得るという目的はついに果たせず、がっかりして故郷に帰ります。
この叙事詩から分かることは、約4000年前のメソポタミアの人びとも死を恐れていたこと、可能であるなら不死になりたいと思っていたこと、しかし不死になるのはどうやら無理そうなので、なぜ不死になれないのかを物語(神話)をつくることによって説明・納得しようとしていた(※)ことです。
※神話には原因譚の機能がある。詳しくは神話と宗教の機能を考えるを参照。
『ギルガメシュ叙事詩』は、人類が造った叙事詩として最古のものであるだけでなく、「不死の追究」をテーマにした物語としても、最古のものです。この後、不死の追究はさまざまな物語において繰り返しテーマになるため、それが人間の心の根底にある願いであることが分かります。『ギルガメシュ叙事詩』について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。

不老不死とは変化しないこと、時の流れの外にいること
前章にて、不老不死が人間の根元的な願いであることを明らかにしました。本章では、不老不死であることが、どういう状態なのか、深く考えていきます。
以前、「ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』の考察」の記事にて、不老不死とは、変化しない状態であることと述べました。
通常、人間を含めたあらゆる生命体は、生まれた瞬間から死に向かって「成長」あるいは「退化」します。例えば、発芽した植物はやがて花を咲かせて枯れるし、生まれた子羊はやがて自らの子を持ち死にます。言い換えると、生きているものはみな変化しつづけます。
ところが、不老不死の者は、変化することがありません。「変化する」ことを「生きている状態」と定義するとき、その反対である「変化しない」ことは「生きていない状態」と定義できます。そのため、不老不死の者は、「死なず」の意味を持ちながら、実は死んでいるのと変わらない状態であることを、先の記事にて述べました。ユング派心理学者である河合隼雄も、以下の通り述べています。
人間が成長してゆきくとき、それは単に生命を維持するだけではなく、時と共に成長変化するということが含まれている。子供が大人に、娘が母親に、と変容するとき、そこには質的な変化が生じるのであり、人間にとってこれは極めて大切なことである。極端に言えば、昨日よりは今日、今日よりは明日と、進歩変化していなくては死んでいるのに等しいということになる。
河合隼雄『昔話と日本人の心』岩波書店、2002年、56-57頁。
しかし最近、『ギルガメシュ叙事詩』などを読み、メソポタミア神話について理解を深めたことで、この状態からさらに思索を深めることができました。メソポタミア神話においては、不老不死の存在としてまず神が存在し、その下僕として、死すべき運命が定められた人間が存在します。思えば、他の地域の神話の例をとっても、不老不死の存在はたいてい、神あるいは神に近しい超自然的な存在です。例えば、冒頭で紹介した北欧神話のエルフも、もとは神の末席に位置していました。
すなわち、不老不死の者は、「死んでいるのと変わらない状態」というよりは、そもそも「生きている」や「死んでいる」などという概念から超越した世界に暮らす者なのです。ここで、ダンセイニの『エルフランドの王女』で描写された、「時間の流れがない」エルフランドの概念もヒントにしてみると、不老不死の者は、人間が暮らす世界とは別の、異界に暮らす存在である可能性が高いことが分かりました。両者の世界を対応表にしてみると、以下の通りです。
| 日常世界(こちら側) | 異界(あちら側) |
|---|---|
| ・時間の流れがある ・人間が暮らす →限りある命をもつ=変化する | ・時間の流れがない(時間という概念がない) ・超自然的な存在が暮らす →永遠の命をもつ=変化しない |
繰り返すと、不老不死の者は、「日常世界」対する「異界」(※)に暮らしている、時間の流れを超越した存在です。しかも彼らが暮らしているのは、異界といっても怪物などの汚らわしい者はいない、神性をおびた者のみが暮らす上位世界です。上位世界はキリスト教的にいえば天国、神道的にいえば高天原に相当します。
※英雄の属性をもつ主人公が、日常世界から異界に旅立ち、目的を果たして日常世界に帰還する、というプロットは冒険物語の典型でもある。『ギルガメシュ叙事詩』も、ギルガメシュが故郷から賢者の住む異界へ旅立ち、故郷に帰還する、というプロットで読むことができる(彼の場合、目的は果たせなかったが)。冒険物語について、詳しくは『ハリー・ポッター』でハリーがニワトコの杖を捨てる理由を参照。

まとめると、不老不死とは、変化しない状態であることに加えて、時間という概念の外にいる状態ともいえます。
不老不死の状態は幸せなのか
人間は昔から不老不死を希求してきました。しかし、仮に不老不死になる方法があったとして、不老不死になることは本当に幸せなのでしょうか。
前章の内容を振り返ると、不老不死の者は異界に属する者です。そのため、あらゆる生命体がいつか死ぬことを定められた、人間の世界においては、不老不死の者は異質の存在です。そのとき、人間界にいる不老不死の者は、他の人間と自分を比べて、孤独にさいなまれることでしょう。なぜなら、どれだけ仲の良い友人や家族がいたとしても、彼らと一緒に年老いて死ぬことはできないからです。よって、人間にとって不老不死の状態は不幸であるといえます。

不老不死になった者が苦しむ物語の例として、ラーゲルクヴィストの『巫女』を紹介します。物語は1世紀ごろのデルフォイが舞台になっています。デルフォイは古代ギリシアにおいて、アポロン神から下される予言、「デルフォイの神託」で有名でした。古代ギリシアの人びとは、自分の運命を知りたい場合、デルフォイに赴き、アポロンに仕える巫女の口を通じて、神託を得るのでした。

有名な例だと、都市国家アテネは、アポロンの助言に従い戦争の準備を進め、ペルシア軍に勝つことができたんだよ(ペルシア戦争)。


物語は、かつてデルフォイの巫女として奉仕していた老女の元に、自分の運命を知りたいという男が訪ねてくることで始まります。男は最初、デルフォイの神殿に赴きましたが、そこで目的を果たせなかったため、高名な巫女として町の人に知られていた、老女に助言を求めにやってきたのでした。老女が、何があったのかと尋ねると、「”神の子”であると噂されている者から呪いをかけられた」と男は答えます。事の次第は次の通りです。
妻と幼い子供と幸せに暮らしていた男は、ある日、これから磔になる死刑囚が、家の前を通り過ぎていくのを見ました。と、その死刑囚が、疲れた様子で、男の家の壁にもたれかかれました。男は、死刑囚に寄りかかられたら、この家に不幸がもたらされるのではないかと不安に思いました。そこで、家の前から去るように、死刑囚に注意しました。すると死刑囚は、「お前の家に頭をよせかけてはならないというならば、お前の魂は永遠に救われぬぞ」と凄味をおびて言います。「お前がこのことを私に拒んだからには、私より重大な罰を受けるであろう。お前は決して死ぬことはない。永遠にお前はこの世をさまよい歩き、決して安らぎを見つけられぬであろうよ」
男は、死刑囚の言ったことなど、気にしないよう努めました。しかし、彼の顔や言葉が忘れられません。後から聞いた噂では、死刑囚はある人々の間では「神の子」と言われていることが分かりました(物語中では明記されていないが、死刑囚はイエス・キリストを指すと推測できる)。男の様子がおかしいことで、近所の人や家族は、彼を恐れて、彼を避けるようになりました。独りぼっちになった男は、故郷を去り、巫女の元に助言を求めてやってきたのでした。


男は、自分の心情を以下の通り巫女に説明します。
不思議だ、あの男が、私は永遠に生かされる、決して死ぬことがないと言ったなんて。実に奇妙だ……これに何の異論があろう。死ぬ必要がない、決して死なないなんて、これこそ俺の究極の願いではなかったか? なのになぜ喜べない? なぜそのことに幸せを感じないのか?
「永遠に……そして、決して安らぎを見つけられぬ……」
これまで一度もじっくり考えたことはなかったけれども、今、永遠というものがどんなことか分かりかけたみたいでした。永遠が私から人生を奪おうとしていることが、永遠それ自体が断罪、不幸そのものであり、それが私の魂を惨めにしようとしていることがです。
永遠……これは生きることとはおおよそ縁のないものなのだ、と私は思いました。これはあらゆる生の反対物ではないか。限りないもの、終わりないもの、生きている者が畏怖をもって覗き込まねばならない冥府なのだ。そして、この冥府に俺は住まねばならないのか? だからこれが俺に与えられたのか? 「永遠に……」これはおれの死刑宣告だ、考え得るなかで一番残酷なものだ。
(中略)
なぜ俺はこんなものを受け入れなきゃならないんだ! こんな気違い沙汰を! 俺のなかに入り込んできたこの力に歯向かい、なぜ言わないのか。「嫌だ! 嫌だ! 俺は生きたい、他の人と寸分違わぬ生を生きたい、元の自分に戻りたい! 他者と同じになりたい! 俺は生きたいのだ!」と。
ラーゲルクヴィスト『巫女』山下泰文訳、岩波文庫、2002年、24-26頁。
こうして、不老不死になった男は、自分の生と、他人の生がもはや異なることに気づき、永遠に生きることは不幸である、という結論に至るのでした。永遠に生きる定めにもかかわらず、「俺は生きたいのだ!」と叫ぶ場面は、矛盾しているようで、「他の人と同じように生きたい」という意味で真実なのです。
結局、不老不死の状態は、人間には喜びをもたらしません。前述した、『ギルガメシュ叙事詩』に登場する酒屋の女主人は、不死を追求するギルガメシュに、以下の通り言います。
ギルガメシュよ、あなたはどこまでさまよい行くのです
『ギルガメシュ叙事詩』第十の書板、三1-14、矢島文夫訳、ちくま学芸文庫、2024年
あなたの求める生命は見つかることはないでしょう
神々が人間を創られたとき
人間には死を割りふられたのです
生命は自分たちの手のうちに溜めておいて
ギルガメシュよ、あなたはあなたの腹を満たしなさい
昼も夜もあなたは楽しむがよい
日ごとに饗宴を開きなさい
あなたの衣服をきれいになさい
あなたの頭を洗い、水を浴びなさい
あなたの手につかまる子供たちをかわいがり
あなたの胸に抱かれた妻を喜ばせなさい
それが〔人間の〕なすべきことだからです
女主人は、ギルガメシュの旅の結果を予言し、人間であるという身の程を知れ、と忠告しています。しかし、これまで本記事に記載してきたことを踏まえて読むと、この台詞は「人間は人間らしく生きることで幸せになるのだから、今ある幸せを大事にしなさい。不老不死になっても幸せにはなれませんよ」と諭しているようにも思えます。そうであるなら、女主人は幸福の真理を悟っていたといえるでしょう。
おわりに
今回は、物語における不老不死をめぐる考察をしました。
はじめに、前近代の人びとにとって、最も恐ろしいことが「死ぬこと」あるいは死に近づくという意味で「老いること」であると説明しました。そのため人間は古来、不老不死になることを願ってきました。
次に、不老不死の状態とは、第一に「変化しないこと」、第二に「時の流れの外にいること」であると定義しました。不老不死の者は、「日常世界」対する「異界」に暮らしている、時間の流れを超越した存在なのです。
最後に、不老不死になることは、人間にとって不幸であると結論づけました。なぜなら、不老不死になった者は、その瞬間から家族や友人とは異質の存在になり、彼らと同じ生を生きることができないからです。
以上、不老不死をめぐる考察でした。
考察に役立った本
J.R.R.トールキン『指輪物語』:永遠の命をもつエルフという存在を知った。エルフのアルウェンと人間のアラゴルンの恋の間には、寿命の違いという障壁がある。不老不死の状態は、ふつうの人間と異なるという点で、実は不幸なのでは?と考えるきっかけになる。『指輪物語』については、過去にもさまざまな記事で記載しているが、代表記事はこちら:『指輪物語』でフロドが灰色港から旅立つ理由。
ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』:不老不死とは、変化しない状態のこと、という洞察を得る。本書を読んでから、不老不死について考察し、記事にまとめたいと思いはじめる。純文学が好きな人にも安心して勧められる、非常によくできたファンタジー物語。関連記事はこちら:ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』の考察。
河合隼雄『昔話と日本人の心』:河合隼雄はユングの孫弟子。「進歩変化していなくては死んでいるのに等しい」という文章を見つけたとき、自分と同じ考えの人がいた!と嬉しくなった。しかし、この時点ではまだ、不老不死の考察が、記事に記載するほどのボリュームになることが想像できなかった。昔話について興味がある方は、昔話とファンタジー小説の共通点の記事もおすすめ。
『ギルガメシュ叙事詩』:解説として本村凌二『多神教と一神教』も併せて読んだ。これだ!!と思った。この本を読んでやっと、不老不死について記事にまとめられる、と確信できた。着想からすでに3年ほど経っていた。ありがとうギルガメシュ叙事詩。関連記事はこちら:世界最古の英雄冒険譚!『ギルガメシュ叙事詩』の魅力。
ラーゲルクヴィスト『巫女』:記事を書こうと思っていた矢先に、たまたま手に取った小説。古代ギリシアの巫女について興味があったから手に取ったのだが、読み進めてすぐに、不老不死の呪いをかけられた男が登場する。なんてタイミングがいいんだ。小説としても、人間の複雑な心情がうまく描写されていて傑作だった。絶版なので図書館で借りて読んでください。あまり知られていないが、ラーゲルクヴィストは1951年のノーベル文学賞作家である。