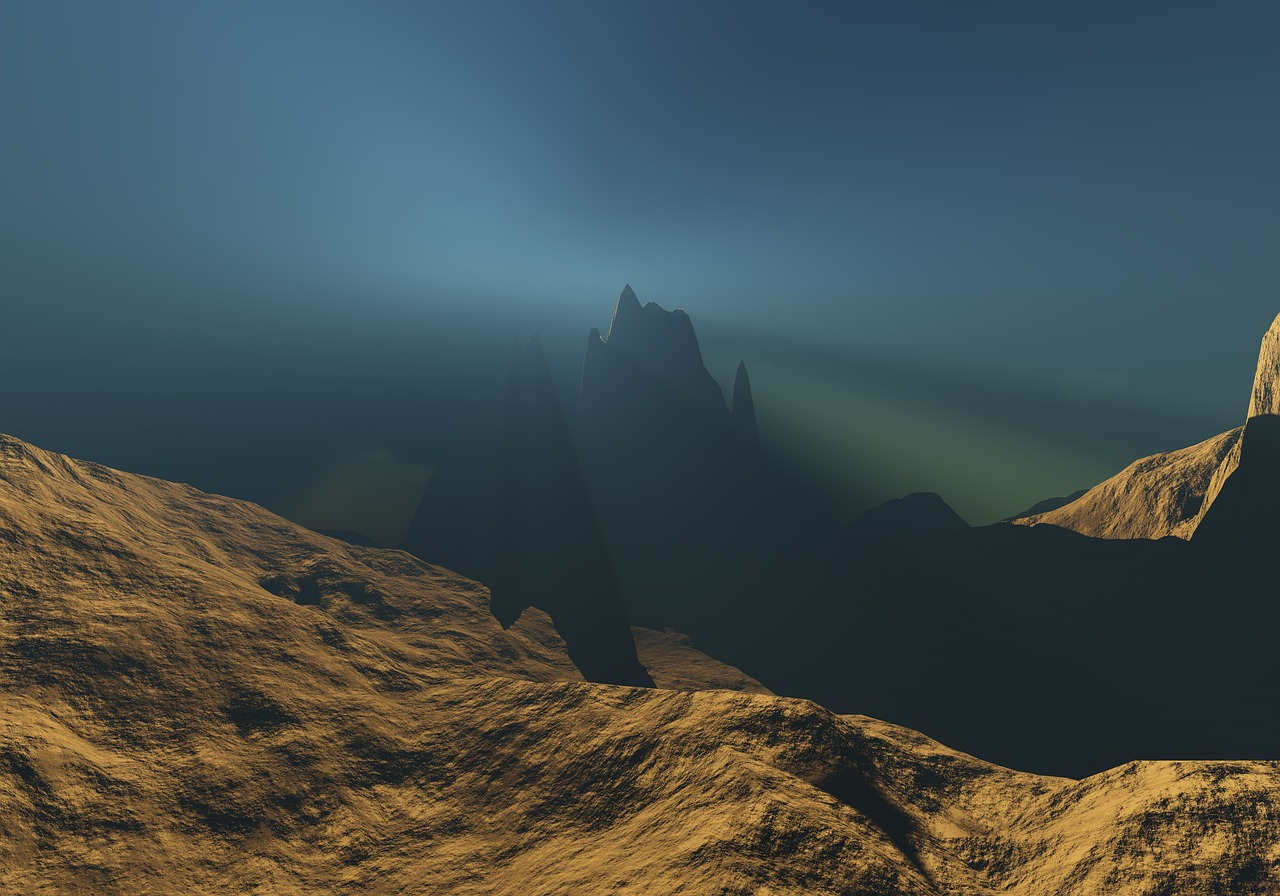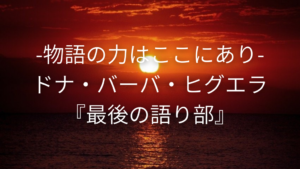あらすじ
物語は、主人公のドローゴが士官学校を卒業し、将校として最初の任地へと出立する場面から始まります。21歳のドローゴは青春の盛りで、士官学校時代の辛い勉強の日々、軍曹の叱責を思い出しては、もうそれらに悩まされることはないのだ、これから輝かしい本当の人生が始まるのだと期待に胸を膨らませます。「最初の任地」となるはずだった、見捨てられた砦、バスティアーニ砦でその長い一生を終えるとは知らずに……。
「タタール人が攻めてくる」という幻想
「北の国」との国境線にバスティアーニ砦はあります。新堡塁から見える「北の国」は、荒涼とした、霧がかった大地です。大昔にタタール人がいたという伝説から、その大地は「タタール人の砂漠」と呼ばれています。ですが、その国境線ではいまだかつて敵が攻めてきたことも、戦が行われたこともありません。毎日毎日、同じ景色が広がり人影ひとつ見えません。実は、砦は一度もその役目を果たしたことがないのです。
ここに配属された将校は「ハズレ」なのです。将校たちはみな、周りに何もなければ事件も起きない、この退屈な砦を出たいと思い、常に出る機会をうかがっています。ドローゴもその1人で、最初は4か月で砦を出ると決意していました。
ところが、砦に長く居続ける将校たちがそうあってほしいと期待する(自分は人生を浪費しているのではないと思いたい)「タタール人がそのうち攻めてくる」という幻想に、ドローゴも囚われ始めます。「あと少しすれば攻めてくるはずだ」、そう思いながら2年が過ぎ、4年が過ぎます。
すると、ドローゴは休暇で帰った町の暮らしに、もはや馴染めないと気づきました。婚約者への愛は冷め、兄弟が独り立ちした実家はがらんとして寂しく、砦での暮らしが恋しくなります。もはや彼の居場所は砦しかなく、後戻りできないところまで時は過ぎていたのです。多くの仲間たちが砦を去るなか、ドローゴは砦に残り続けます。
なぜか頁をめくり続けてしまう本
『タタール人の砂漠』は、これといった事件も起こらないのに、なぜか引き込まれ、頁をめくり続けてしまう本です。それはおそらく、ドローゴと共に、わたしたちも「いつかは戦が起きるはず」という期待を抱いてしまうからです。
ドローゴは「自分の一生がこんなつまらない一生で終わるはずがない、自分はいつか英雄となるのだ」と思い、読者は「主人公の一生がこんなつまらない一生で終わるはずがない、だって彼は主人公なのだから」と思い、彼と一緒にタタール人の襲撃を待ち続けます。だから、思わせぶりな噂がたつたびに、「今度こそタタール人が攻めてきたかもしれない」と思いハラハラドキドキするのです。
実際にタタール人が攻めてくるかは、ぜひ本を読んで確かめてみてください。
ドローゴは人生そのものを具現化した人物
イタリア文学者であり、『タタール人の砂漠』の翻訳者である脇功(わきいさお)氏は主人公ドローゴについて次のような解釈をしています。
繰り返すが、この作品の主人公は人生というもの自体であり、ドローゴ中尉という人物は人生そのものを具現化したものである。孤立した辺境の砦に勤務する主人公に限らず、いかなる職業であれ、ずっと同じ仕事に従事し、そうした意味では閉鎖的な、単調な日々を過ごさざるを得ないのが、大多数の人々の人生である。そして人々はそうした日々に耐えるために、なにか価値ある出来事が起きるのではないかという幻想を、期待を抱き、それがむなしいものにすぎないかも知れぬと思いながらも、心の内にひそかにそれを保ち続ける。しかし、その間にも時は容赦なく流れ去る。
ブッツァーティ『タタール人の砂漠』脇功訳、岩波文庫、2016年、P. 346
どきっとしますね。「でも、自分だけはこうならないはず。自分はきっと夢を叶えて満ち足りた人生を歩むのだ」と読者は思います。ですが、ドローゴと一緒になって、タタール人が攻めてくることを期待してしまう読者は、ドローゴと変わらない思考をしているのです。自分のなかでは自分が主人公で、きっと未来に価値ある出来事が起こるはずだと信じ続けているのです。
もしかしたら道を誤っているのかもしれないし、もう戻れないところまで歩んできてしまっているのかもしれません。ですがそれは人生が終わってみないと分からない、大きな賭けなのです。どんな結果になるにせよ、「これでよかったのだ」と納得できる人生が幸せなのかな、そんなことを考えさせられる小説でした。
以上、『タタール人の砂漠』の感想でした。