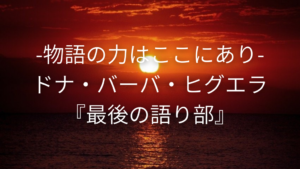はじめに
日本人は世界の他の民族と比較すると、月に対する強い愛着を持っている。月を愛でて、歌に詠む文化は独特なため、日本人の精神世界が月を中心に成り立っていると考える外国人もいるほどだ。例えば、ローレンス・ヴァン・デル・ポストはその考えを『影の獄にて』(映画『戦場のメリークリスマス』の原作)において書いている。※詳しくは過去記事を参照。
しかしながら、月を好むのは日本人だけではない。それは「月」を題名に取り入れた小説が、世界中にたくさんあることで説明できる。有名な例を挙げると、サマセット・モームの『月と六ペンス』がある。
そんな題名に「月」が入っている小説のなかでも、私のお気に入りは、チェーザレ・パヴェーゼの『月と篝火』だ。パヴェーゼが若くして自殺する前に書いた最後の小説で、彼の最高傑作と言われている。非常に美しく完成された小説のわりに、知名度が低いため、この記事で魅力を綴りたい。
※ザ・純文学なため、ネタバレしても楽しめるタイプの小説です。

物語の概要
物語の舞台は、ファシズムと第二次世界大戦の爪痕が残るイタリアの寒村だ。主人公の「ぼく」は、その村で私生児として育ち、やがてアメリカで財をなして、村に戻ってきた。村に戻ってきたのは、かつての自分が養子として住んでいた家や、下男として働いていた農場の様子、村人たちの様子が知りたかったからだ。「ぼく」は村にいる間、幼馴染で知恵者のヌートと、今の村の様子や過去の村の様子、戦争のことなどを話しあう。そして、半月の休みが終わるころに「ぼく」はまた仕事へと帰っていき、物語の幕が閉じる。主人公の帰郷がテーマの物語だ。
パヴェーゼが物語に込めたもの
パヴェーゼは学生時代、フレイザーの『金枝篇』に没頭していた。古代ローマ時代のネミの祭司の風習を中心に、世界のあらゆる信仰に共通するものを紐解こうとする『金枝篇』については、過去の記事でも何度か取り上げてきた。詳しくは神話と宗教の機能を考えるを参照。
よってパヴェーゼは、自身の物語に神話的な深みをもたらすことを試みた。つまり『月と篝火』は、表面上だけ読むと主人公の生い立ちの物語だが、さらに深く読もうとすると、それぞれの登場人物や場面に別の意味が込められていることに気づく。
例えば、主人公が下男として働いていたモーラの農場主には、3人の美しい娘がいた。それぞれの名前が、イレーネ、シルヴィア、サンティーナなのだが、イレーネはギリシア神話の平和を司る女神エイレーネー、シルヴィアはラテン語のsilva(野生の森)、サンティーナはsantaつまり「聖女」に由来している。すなわち3人は「平和」「原始の森」「聖女」を象徴していると考えられる。そして彼女たちがたどった人生を考えると、平和も原始の森も失われるし、聖女は戦争の生贄になるのだ。
この物語の題名である、「月」と「篝火」も、表面上は洗礼者ヨハネの祭でたかれる炎と、その夜に輝く月を表している。あるいは、農作物の出来栄えを左右するものとして登場する(例えば篝火を炊いたあとの土は畑のよい肥しになる)。しかしそれらには別の意味も込められていて、特に篝火は、生と死の循環の神話を表していると考えられる。
※ちなみに、夏至(洗礼者ヨハネの祭)に篝火を焚くのは、古代信仰のなごりである。夏至と冬至については、西洋になぜキリスト教が浸透したのかでも紹介している。
望むのは季節であって歳月ではない
パヴェーゼの神話については、難しくて私にはすべてを解明しきれない。そのため、ここからは作中のお気に入りの表現を紹介したいと思う。
お気に入りの一つ目は、主人公が自分が育った村に対し、昔のままであってほしい、と望む表現だ。あらゆる町や村は歳月の流れとともに変化してゆき、ある日ひとは、自分が子供時代を過ごした故郷はもはや存在しないことに気づく。主人公はそれを悲しみ、自分は歳月の流れではなく、永遠に変わらない季節のめぐりを望んでいるのに、と表現する。
どうやって人に説明できただろう。ぼくが求めているのは、かつて見たことがあるものを、ふたたび見たいだけだ、などと? 荷車を見たい、干し草置き場を見たい、葡萄の桶を、鉄柵の門を見たい、チコリの花を、青いチェックのハンカチを、瓢箪を、鍬の柄を見たい、などと? かつて見たことがあるのと同じように、人びとの顔を見るのも楽しみだった。皺をきざんだ老婆、用心ぶかい牝牛、花柄の服の娘たち、鳩小屋のような屋根。ぼくにとって、過ぎ去ったものは季節であり、歳月ではなかった。ぼくの身に触れてくる事物や会話が、昔のものと――ぼくが世界へ出て行くまえの、土用の暑さ、市場、かつての収穫などと――同じであればあるほど、ぼくには喜ばしかった。そしてスープも、葡萄酒の壜も、鉈(なた)も、麦打ち場の丸太も。
パヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳、岩波文庫、2014年、84頁。
カネッリはカネッリであるがゆえにぼくは好きだったのだ。そこに集まってくる谷間や丘や土手と同じように。ここですべてが終わりになるから、歳月ではなく季節が交代する最後の町であるから、ぼくはここが好きなのだった。
同上、87-88頁。
さまざまな場所を旅したが誰も知らない
星野道夫という、アラスカの自然や動物を撮り続けた写真家がいる。私は写真の前にエッセイで彼のことを知り、特に『旅をする木』が傑作だと思っている。あらゆる生命はいつか土に還り、他の生き物の一部となってまた旅をはじめる。そんなことがアラスカでの暮らしを通して分かるエッセイだ。
彼のエッセイのなかで、印象的だった文章がある。それが以下だ。
人が旅をして、新しい土地の風景を自分のものにするためには、誰かが介在する必要があるのではないだろうか。どれだけ多くの国に出かけても、地球を何周しようと、私たちは世界の広さをそれだけでは感じ得ない。が、誰かと出会い、その人間を好きになった時、風景は、はじめて広がりと深さをもってくる。
星野道夫『長い旅の途上』2021年、文春文庫、38頁。
人を知ることは世界を知ることである。人は別の誰かとつながりを持つことによって、その人を通して世界を見ることによって、はじめて新しい世界を知ることができる。よって世界を知るためには、いたずらに旅をすればいいというものではないのだ。
同様の表現が、『月と篝火』にも出てきた。主人公がイタリアを離れて、アメリカを放浪しているときの話である。
やがて、あの南の道を、やたらに突き進むのもやめた。それはあまりにも大きい国だったから、どこかへ着くということがなかった。ぼくはもはや、鉄道員の仲間たちと八カ月かかってカリフォルニアに着いたときの、あの若者ではなかった、たくさんの村を知っていることは、誰も知らないことだ。
前掲書、91頁。
主人公は東海岸に上陸した後、西海岸のカリフォルニアまで行った。つまりアメリカを横断したことになる。しかし、さまざまな場所を訪れて、さまざまな人と出会っているにもかかわらず、彼は誰のことも知らないのだ。アメリカでは故郷とちがって、人とのつながりがないから。それはとてもむなしく、悲しいことだ。
無知の代償
第二次世界大戦中、イタリアではムッソリーニ主導でファシズム(議会制民主主義を否定する独裁政治)がしかれていた。それに反乱するために生まれたのが、パルチザンと呼ばれる、正規軍と闘う非正規軍の人びとだ。『月と篝火』の作者であるパヴェーゼ自身も、第二次世界大戦下でパルチザンとして活動しており、物語には反ファシズムの思想が流れている。例えば、主人公とその幼馴染ヌートは、作中でパルチザンであることがほのめかされている。
パヴェーゼは自分の大切なものを自分で守るために、知識が必要であることを示唆している。その思想は作中で、下男から知識を身につけ、立身出世した主人公の成長の過程に投影されている。時代を越えて人びとの教訓になる大切な考えだと思うので、以下にいくつか引用したい。
それにヌートを好きになれたのは、話が合ったからであり、ぼくを友だちとして扱ってくれたためだった。そのころから彼は、もう猫のように、鋭い目をしていた、そして自分が言ったあとで、必ずつけ加えた。《まちがっていたら、ぼくを直してくれたまえ》こうして話すことは《これをした》《あれをした》《食べた、飲んだ》というような、おしゃべりだけでなく、自分の考えを生み出すことであり、この世界の仕組みを理解することである、とぼくは知った。それまでには、思いもかけないことだった。そしてヌートはそれに長けていた、まるで大人だった。
前掲書、138-139頁。
(モーラの農場の屋根裏部屋で、ヌートは本をみつけた。)ヌートはセーターの下にその何冊かを隠して家へ持ち帰った。《どうせ――と彼は言った――誰も使っていないのだから》「そんなもの、どうするの?」とぼくは彼に言ったことがある、「きみの家じゃ、もう新聞をとっていないの?」(ヌートは主人公に、新聞を読んで世界のことを知る大切さを教えていた。)
「これは本だよ」と彼は言った、「きみもなるべく読むんだよ。本を読まなければ、いつまでたっても、きみはきみのままなのだから」
前掲書、162-163頁。
「覚えているかい、きみ(=ヌート)の家の店先でお父さんと話したときのことを? あのころからきみのお父さんは言っていた、無知な人間はいつまでたっても無知だろう。なぜならば権力は、人びとが無知であることによって利益を得ている連中の手に、政府の手に、黒衣の連中に、資本家たちの手に、握られているのだから……(後略)」
前掲書、212-213頁。
古代ギリシアのアテナイ(アテネの古名)の政治家アイスキネスも、次の通り言っている、「国民が知識を身につけ嘘を見抜けるようになれば国力が増す」。人が他者を騙すことによって生存をはかる生き物なのだとしたら、私はとても悲しい。しかし現実として、一部の人が莫大な利益を得るために、嘘も汚職も横行している。人類の共同体において、権力者からの搾取を察知しそれを防ぐには、知識と自分で考える力が必要なのだ。
万物は流転する
最後に、文章の流れと言い回しがとても美しいと思った部分を引用しよう。あらゆる物体は生まれて死ぬという、生と死の循環や、主人公がまるで根無し草のように放浪するだろう(万物は流転するだろう)、という予感が表現されている。
汽車に乗ればどこへでも行けるし、鉄道が終われば港が始まり、船は定刻どおりに出航して、世界じゅうの道と港は交差し、時刻表にのっとって人びとは旅をし、物事を作ったり壊したりしている、そしてどこにでも有能な人間と無能な人間とがいるのだ、と言ったのは、やはりヌートだった。彼はいろいろな国の名前も教えてくれた、それらの国のことを知るには、新聞を読みさえすればいいのだ、とぼくに言った。こうして、道の上の葡萄畑や、野良で、太陽に照らされながら鍬を振るっていたとき、桃の林を縫って近づいてくる汽車の音を、ぼくは聞いた。轟音は谷間を満たし、カネッリへ遠ざかり、またカネッリからやって来た。その移りゆく瞬間に、鍬にもたれたまま、身じろぎもせずに、ぼくは見つめていた。機関車の煙を、連結した車輛を、またガミネッラの丘を、《鳥の巣》の小さな館を、カネッリや、カラマンドラーナや、カロッソの方角を。すると葡萄酒を飲んだあとみたいに、自分が別人に、ヌートになったみたいに、彼と同じ価値を身に備えたように感じて、いつの日か自分もまたあの汽車に乗って旅立つだろうと思うのだった。どこへ行くのかは知らぬが。
前掲書、141頁。
おわりに
今回はパヴェーゼ『月と篝火』の感想をつづった。
哀愁ただよう一人称語りがとても好みだし、純文学らしく教訓に富んでいるのもよい。文章表現も美しく秀逸だ。パヴェーゼの真意(神話)を読み取ろうとしなければ難しくない小説なので、ぜひ皆さんにも読んでもらいたい。
ちなみに、今回再読したのは、今度の読書会で紹介したい本だったからだ。以上、『月と篝火』の感想だった。