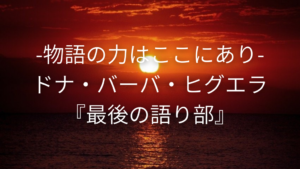はじめに
1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』(英: Merry Christmas, Mr. Lawrence) は日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの合作映画です。第二次世界大戦中のジャワ島における日本軍捕虜収容所を舞台とし、日本兵とイギリス人捕虜の複雑な人間関係が描かれています。主題歌は作中でヨノイ大尉役を演じた坂本龍一により作曲され、英国アカデミー作曲賞を受賞しました。(聞きたい方はこちら→https://youtu.be/ZY5J03EDe9k)
映画の原作は『影の獄にて』(英: The Seed and the Sower, 種子と蒔く者 )という、イギリス国籍の作家ローレンス・ヴァン・デル・ポストが書いた小説です。
ヴァン・デル・ポストは現在の南アフリカ共和国出身のボーア人貴族の家系に生まれました。ボーア人とは、1620年に宗教上の迫害をのがれてオランダから南アフリカの喜望峰に達し、その地にコロニーを営んだ人を祖先とする人びとのことです [1]。彼は1926年、アフリカを訪れた日本人船長と共に日本へ行き、約2カ月滞在しました。その後、第二次世界大戦が勃発し、ジャワ島の日本軍捕虜収容所で約2年間の辛い日々を送りました。その時の体験を中心に執筆されたのが『影の獄にて』です。
ヴァン・デル・ポストの作家としての重要な三柱は、「アフリカ」「日本」そして「ユング」であると訳者の由良君美氏は述べます。深層心理学者のユングと交友関係があった彼の作品には、ユング心理学の大きな影響が見られます。『影の獄にて』の主題の一つも、心理学用語としての「影」であると考えられます。
今回は、映画をまだ観ていない方や、原作を未読の方を対象に、原作に基づいて『戦場のメリークリスマス』の解説をします。ネタバレするのでご注意ください。
原作の概要
原作『影の獄にて』は三部に別れており、それぞれ以下のタイトルとなっています。一見、意味の分からないタイトルに思えますが、読み終えると納得な、主題を反映する上手な暗喩になっています。
- 第一部「影さす牢格子」
- 第二部「種子と蒔く者」
- 第三部「剣と人形」
物語は戦後のとあるクリスマス前夜に、語り手の「わたし」と旧友のロレンスが再会する場面から始まります。そして「わたし」の家族とロレンスがクリスマスを共に過ごしながら、戦時における三つの記憶を振り返ります。その三つの話が、紙面上では三部に分かれているというわけです。
第一部はロレンスとハラの話、第二部はジャック・セリエとその弟、そしてヨノイの話です。第三部は映画でロレンスがちらっと口にする、ロレンスが愛した女性と彼の話です。
映画のストーリーは第一部と第二部を組み合わせた内容です。原作では別々の時と場所で起きた出来事ですが、主題と鑑賞者へのメッセージは原作と変わらず、原作に忠実にできています。ただし詰め込みすぎた感があり、映画のみ観てもメッセージがうまく伝わらないかもしれません。その理解補助としても、本記事が役に立てば幸いです。
ちなみに原作では、ロレンスとセリエは戦友であるものの、ジャワ島(映画の舞台)では同じ時を過ごしません。そして日本人のハラとヨノイも同じ時を過ごしません。
ロレンスとハラ
ロレンスは奇妙な男です。彼は、戦前に日本に滞在したことがあり、日本の文化をよく理解した、日本語を話すことができる人物として登場します。もうお気づきかもしれませんが、彼の経歴は作者のヴァン・デル・ポストにそっくりです。ロレンスは、作者自身の経験が最も投影された登場人物であると言えます。
彼はこの物語で最も重要な役割を担っています。異なる二つのものを繋ぐ仲介者として、あるいは解説者として登場します。最も際立って現れるのはイギリス人と日本人を繋ぐ仲介者としてであり、そのほか意識と無意識、女性原理と男性原理など、原作の語り手「わたし」に考えを示唆する解説者として登場します。
日本陸軍の軍曹であるハラと関わるとき、ロレンスと彼の間には、以下の通りの対立関係が生まれます。ロレンスは「個人」「自由」「生」を象徴しており、ハラは「集団」「不自由」「死」を象徴しています。
| ロレンス | ハラ |
|---|---|
| 個人 | 集団 |
| 自由 ※ | 不自由 |
| 生 | 死 |
※ただし限られた範囲での「自由」。ロレンスが言うには「おのれを閉じこめる人生の鳥かごを、みずから選ぶ自由」36頁
個人と集団
ロレンスはハラを好いています。そしてハラもロレンスを好いています。彼らの間にあったのは一種の友情と言えますが、語り手である「わたし」はやや納得できません。
なぜロレンスはそこまでハラを気にいっているのか?一介の軍曹にもかかわらず収容所は「ハラの支配する牢獄」でした。ハラはそこで圧倒的な存在感を持ち、彼の目に留まることをみな(イギリス人捕虜)は恐れていました。特にロレンスは彼のために殺された人をのぞけば、獄内でもっとも酷い目にあった男でした。
ある日、獄内で、ものすごくぶたれたあと、彼がこう言ったのを、わたしは今でもはっきりと覚えている。
「いいかね、君がハラという男について忘れてはならないことはだ」と彼は言った。「彼は個人でもなければ、本当の意味で人間でもないということなんだよ。」
L・ヴァン・デル・ポスト『影の獄にて』由良君美、富山太佳夫訳、思索社、1985年、13頁。
上記の言葉に、ロレンスがハラという人間をどう捉えていたのかが集約されています。
まず「個人ではない」という言葉には、ハラが集団に従うために、個人的意志を殺している人間であることが示唆されています。ハラは「完全に無私」(13頁)で、「個人として生きる資格を拒絶」(30頁)した、「群れの行うことにはすべて従う」(19頁)人物であると説明されます。そして「彼ら(収容所を支配していた日本軍)のなかでももっとも日本人だった」(20頁)という言葉には、ハラが集団意志に従う日本人としての代表だったことが示唆されています。そのためにハラは、個人としてはロレンスを非常に好いていながらも、集団としてそうしなければならないときには、ロレンスを手加減なく罰しました。
そして引用の「本当の意味で人間でもない」という言葉には、ハラが神話の権化であることが示唆されています。この文脈における神話とは、集団意志を突き詰めた際に表れるおおもと、共同体の団結意識を生んだ神話であると考えられます(※)。
※一般的に、あらゆる神話には人びとの団結をもたらす機能がある。同じ神話を信じている人びとの間には同胞意識が生まれるためだ。西洋人が西洋人として団結できるのは一つには同じ神話(宗教)を根底にしているからであり、日本人が日本人として団結できるのも一つには同じ神話を根底にしているからである。
「いや、彼(ハラ)は自分で自分をどうにもできんのだ」とロレンスは言うのだった。「ああいうことをやっているのは、彼じゃない。彼のなかの日本の神々がやることなんだ。わかるかね?月がどんなに彼の心を動かすか、君も覚えがあるじゃないか!」
同上、14-15頁。
つまり、「本当の意味で人間でもない」という言葉にも、「個人ではない」と同様に、ハラが個を持たずに集団意志に従う人物であることが示唆されています。この前提に基づいて、ロレンスとハラとの関係を見たとき、個の意志に従うロレンスと、集団の意志に従うハラという対立が浮かび上がります。二人は互いの「影」、真逆の性質を持つもう一人の自分だったと考えられます。そのため互いに惹かれ合ったと言うことができます。
自由と不自由
その他の対立項、「自由」と「不自由」、「生」と「死」については、「個」と「集団」から派生してできた対立だと考えられるので、簡単に説明します。
まず「自由」と「不自由」について。彼らが置かれた状況を考えれば、普通は捕虜収容所を監督するハラが自由の身で、捕虜であるロレンスが不自由の身です。しかしロレンスの目にはその逆、ロレンスが自由の身で、ハラが不自由の身に見えます。
その理由は、ハラが「神話という土牢のなかの囚人」(36頁)であるから、つまりハラが集団意志のしもべだからです。もちろん人間に完全な自由などありません…少なくともロレンスはこう考えています。「自由とはおのれを閉じこめる人生の鳥籠を、みずから選ぶ権利である」(36頁)。しかしハラは、このような限られた自由でさえ知らなかった男でした。よって両者を比較した際により自由なのはロレンスであり、不自由なのはハラだったのです。
生と死
次に「生」と「死」について。ロレンスはハラが、というよりハラのなかの日本人の集団意志が、生よりも死を愛していることに注目しています。それは映画中でハラがロレンスに向けて言う、「わしはお前が死んだらお前のことをもっと好きになった」という言葉にも表れています。つまり、ハラ(と彼のなかの集団意志)は敵に捕まって生きるよりは、死ぬほうが好ましいと考えているのです。
この理由についてもロレンスは考察を試みています。ロレンスは、神話において太陽と月を男性と捉えるか女性と捉えるかで、生と死のどちらを愛するかが変わるのではないかと考えています。ご存知のように神道において太陽神はアマテラスであり、女神です。一方で西洋土着の神話において太陽神は男神です(例えばギリシア神話のヘーリオス)。そして神道における月の神はツクヨミであり、一般的に男性と考えられています。一方で西洋土着の神話において月の神は女性です(例えばローマ神話のディアナ)。
上記の違いが、日本人が死を愛する理由ではないか、とロレンスは考察しています。しかしここはそれ以上に深く考察されておらず、いまいち説得感に欠けると個人的に思います。この小説が執筆された時代を考えれば仕方ない面がありますが、ロレンスは「たいていの過去の民族は、太陽というものを、光輝ある男性神と考えた」(32頁)と言っています。明らかに、彼の言う「たいていの過去の民族」には西洋人しか含まれていません。日本民族以外にも、太陽を女神と捉える民族は多く存在するので、ロレンスの論理で考えると、では太陽を女神と捉える民族は全て生より死を愛しているのか?という疑問が生まれます。
説得力の有無はともかく、ロレンスとハラは生と死の象徴としても対立していました。
「メリークリスマス」が象徴するもの
Merry Christmas, Mr. Lawrence ――ビートたけしの演じるハラが、最後に言う言葉です。そして映画のタイトルにもなっている、重要な言葉です。この言葉が象徴しているものは、私が考えるに「人類の希望」です。歴史のなかで繰り返される悪行――「無理解と誤解、憎悪と復讐」(46頁)――つまり結果として戦争に繋がるものが、なくなるかもしれない希望です。
ハラがロレンスに「メリークリスマス」と言った経緯を考えましょう。映画では、ロレンスが無線ラジオを保持していた疑いから、彼に死罰の決定が下ります。ところが、酒に酔ったハラに呼び出されたロレンスは、クリスマスに免じて釈放されます。原作でも、ロレンスは12月27日に殺される予定でした。ところが映画と全く同じ流れで、クリスマスに免じて刑を免除されました。
「個と集団」の章で説明したことを踏まえると、この行為は実にハラらしからぬ行為です。ハラは個人意志を殺し、集団意志に従う人間です。通常ならば、ハラはロレンスを助けたいという私的感情を優先させることはありません。ところが「メリークリスマス」と言ったこの時、ハラは変わろうとしたのです。ロレンスに、つまり自らと対立する個の象徴に手を差し伸べたのです。
時は流れ、自身の処刑が行われる日の夜中、ハラは再度ロレンスに「メリークリスマス」と言いました。これは映画では描かれなかった場面ですが、ハラと別れたロレンスは、この時のハラの表情と目にいたく心を動かされ、彼の元に戻りたい衝動に駆られました。彼をしっかりと腕に抱き、額に口づけをし、こう言いたかったのです。
外の大きな世界の、がんこな昔ながらの悪行をやめさせたり、なくさせたりすることは、ぼくら二人ではできないだろう。だが、君とぼくの間には、悪は訪れることはあるまい。これからゆく未知の国を歩む君にも、不完全な悩みの地平をあいかわらず歩むぼくにも。二人のあいだでは、いっさいの個人の、わたくしの悪も帳消しにしようではないか。個人や、わたくしのいきがかりは忘れて、動も反動も起こらないようにしよう。こうして、現代に共通の無理解と誤解、憎悪と復讐が、これ以上広まらないようにしようではないか
同上、45-46頁。
ロレンスもこの時、変わろうとしたのです。ハラに、つまり自らと対立する集団の象徴に手を差し伸べたのです。しかし士官としての彼がそうはさせませんでした。後悔して戻ったときにはもう、ハラは絞首されていました。
もしハラの処刑が行われる前に、ロレンスの望むことを出来たのなら、「歴史の全工程を変えることができたような気持ちを味わえていたかもしれない」(46頁)とロレンスは回想します。なぜなら、人類の悪行を根絶するには、まず個人個人が小さな変化をすることが重要だからです。彼の言葉で言うと、「個人の心のなかに生じた小さい変化のささやかな種子から始まるもの」(46頁)だからです。(ちなみに「種子」は作品を通じて重要な主題になっており、『影の獄にて』の英タイトル “The Seed and the Sower, 種子と蒔く者” に使用されています。のちほど説明します)
つまり「メリークリスマス」という言葉は、ハラの心に変化が生じた印であり、繰り返される人類の悪行をなくすための第一歩だったと言うことができます。そのため、映画のタイトルにもなっている「メリークリスマス」は、人類の希望を象徴していると考えられます。
セリエ
セリエは原作における第二部の主人公的存在です。セリエは自身が処刑される前、原作における「わたし」宛てに手紙を書いていました。「わたし」とロレンスはその手紙を読みながら、セリエに関する思い出を語り合います。
セリエに関する話は時系列的に二つに分けられます。一つ目がセリエの「裏切り」について、つまり弟との軋轢から和解までの話です。二つ目が弟と和解して再び戦場に戻った後の話、つまりヨノイとの出会いから死までの話です。
セリエが登場する第二部のタイトルは「種子と蒔く者」です。このタイトルは新約聖書における種を蒔く人のたとえ話(マタイによる福音書13章1-23節)に由来しています。種をまくとき、ある種は育ちにくい場所に落ちて芽をださず、ある種は良い土壌に落ちて立派に育ちます。イエスは種に信徒を暗喩しており、御言葉に対する聞く耳をもっているかどうかで、その人が実を結ぶかどうかが決まるという解説をします。
セリエの話においては、まず弟が種蒔く人を象徴しています。弟はセリエに種を蒔きます。セリエが弟と和解した時、セリエのなかで種が実ります。すると今度は、セリエが種を蒔く人の象徴となります。そしてセリエは日本兵とイギリス人捕虜全員に種を蒔き、死を迎えます。この文脈における「種」も、「メリークリスマス」と同様に人類の希望であると考えられます。
弟が種を蒔く

人生においてまず必要なことは、普遍的なものを特殊なものに、一般的なものを特定のものに、集合的なものを個に、われわれのなかの無意識的なものを意識化することなんだ、と言うと、(ロレンスは)突然プツリと言葉を切ってしまった。
同上、151頁
「わたし」とロレンスが読んだセリエの手紙には、彼の人生における「裏切り」の内容がつづられていました。「裏切り」は2つあり、どちらも彼が弟を拒絶した話です。映画では2つ裏切りのうち1つ、すなわちセリエが通う学校に弟が入学した際、「イニシエーション」(新入生に対する通過儀礼)から彼を救わなかった話が紹介されます。
セリエと弟は、生まれた時から正反対の外見と性格を持っていました。外見については、セリエは金髪と白い肌と高い背を持っていましたが、弟は黒髪と浅黒い肌と低い背を持っていました。何より、セリエが均整のとれた体躯をもつのに対して、弟は背にこぶを持っていました。性格については、セリエが周囲の注目を集め常に友人に囲まれているのに対して、弟はいつも一人でした。
この対照的な外見と性格から、ロレンスとハラの関係と同様に、セリエと弟が互いの「影」であることが分かります。つまり、セリエは弟を拒絶することによって、自らのうちにあるもう一つの領域、無意識から逃れていたと考えられます。そうした行為の原因は、彼に対する周囲の期待でした。セリエは自分の本心を差し置いて、他人の期待に自分を捧げていました。セリエは以下の通り回想します。
(前略)わたしはと言えば、人々が即座にもつ磁石的な好意を敵に回し、自分が何処にいるのか、自分が誰なのかわからぬうちに、わたしが人に与える印象の捕虜になってしまうのだった。(中略)わたしは自らの美貌というよりも、人々がわたしを見てまず想像し、つぎに想像力によってわたしに押しつけてきたものにしばられていた。(中略)徐々にしかし確実に、わたしは自分自身からいたましく疎外されたのだ。
同上、56頁。
彼の本心は弟が、つまり無意識の象徴が持っています。セリエは学校を卒業後、弁護士として働きはじめますが、周囲の彼に対する羨望とは裏腹に、セリエは追い込まれていきます。弟への「裏切り」が頭から離れず、影との戦いに消耗し、長く眠れない夜を過ごします。
そんな時に始まった戦争が自分を苦しみから解放してくれるだろうと期待し、セリエは兵士となりました。しかし敵の顔が弟に見えたりと、引き続き影との戦いに悩まされます。ところがある出来事をきっかけに、和解の糸口をつかみます。セリエは最初の休暇を使用して、故郷で農場を営む弟の元を訪ねます。自分のしたことについて謝罪し、本音で話し合い、長い時を経てやっと、セリエは弟と和解したのです。
弟が昔から植えつけや種まきを好み、大人になってから農場を営んでいるのは、彼が「種蒔く人」の象徴であることを示唆しています。セリエは弟(影)から差し伸べられた手を、あまりにも長い間拒絶していましたが、やっと掴みました。弟は兄から拒絶されて以来、ずっと封印してきた得意な歌を、また歌うようになりました。
セリエが種を蒔く

セリエとヨノイが出会ったのは、セリエが弟との和解を果たし、戦場に戻った後のことです。ヨノイは彼を一目見た瞬間から、彼の魅力に憑りつかれてしまいます。一方でセリエは、美男子のヨノイがかつての自分と同様の男であるということに勘づき、「わたし」に対しこう説明しています。
「ヨノイもぼくと同じように、あでやかな羽毛に眼のくらんだ鳥仲間ってとこだろうな。あの男も自分のなかの法から逃亡したのだ――ぼくと同じさ。」
同上、155頁。
つまり、美貌のセリエがかつて周囲の期待の捕虜となり、自分自身から疎外されたように、美男子ヨノイも周囲の期待の捕虜となっていたのです。その気持ちをよく知っているセリエは、ヨノイに対して親近感を抱きます。そして弟から種を蒔かれ、救われたように、今度は自分がヨノイやその部下や同胞に種を蒔き、救う決心をします。
その決心が訪れたのは、ヨノイの命令によって、灼熱の太陽の下、収容所内の捕虜全員(四千名)が整列させられた時のことでした。なぜそのような事態に陥ったかというと、捕虜全員がグルとなって、「捕虜のなかに兵具、銃砲の専門家はいない」と嘘の返答をしたためです。
そのような状況に立たされても、捕虜長であるヒックスリ=エリスの返答は「(兵具、銃砲の専門家は)おりません」でした。激昂したヨノイは刀を抜きます。原作における「わたし」は続きを以下の通り描写します。
機関銃隊員が安全装置をはずし、四丁の機関銃の弾倉に玉がはいる音が大きく響いた。万事休す、とわたしは思った。誰かが何とかしなければ、ひとりひとり首をはねられるーーなんとかしたところで、それでケリがつくわけでもない。この虐殺欲はみたされなければならないし、みたされるまでは、ヨノイや他の奴らの餓鬼が手をゆるめるはずはない。この先どんな手を打とうと、すべてしくじりになって、生き残る者を苦しめるだけだろうーー生き残る者がでればの話だが
同上、175頁。
「わたし」は絶望して、くるりとセリエのほうを向きました。セリエはその時にはもう、決心を終えていました。「わたし」に向けて別れを告げると、隊列から進みでました。彼は行動に出る前に、「わたし」にこう告げていました。
彼は低い声でこう言ったのだ。ヨノイがあんなことをやっているのも、自分に期待されていることを実現しているだけだよ、われわれと同じだ、と。そして、ヨノイに思いがけないことをぶつけてみる以外に、ヨノイやその部下やわれわれを救う途はない。(中略)とつけ加えたのである。
同上、174頁。
こうしてセリエは、ヨノイの頬に頬をすり寄せました。すると事態は一変しました。セリエの取った奇態で思いがけない行為が全員の頭から離れなくなり、日本兵対イギリス人捕虜という構図が、セリエ対その他に変わったのです。セリエは日本兵とイギリス人捕虜の分断に橋を渡し、双方を宿命的に縛り付けていたものから、解放したのでした。
これがセリエの蒔いた種です。映画ではヨノイは戦後処刑されたことになっていますが、原作では数年後に釈放され、自身でセリエの髪の毛を神社に奉納しに行っています。弟からセリエに蒔かれ、セリエからジャワ捕虜収容所に蒔かれた種(人類の希望)は、ヨノイにも、「わたし」にも、ロレンスにも植えられ、彼の死後も各々の心の中で育っているのです。
おわりに
今回は、原作に基づいて映画『戦場のメリークリスマス』の解説をしました。この物語を貫くテーマは「影」と「種子」(希望)であると思います。人は誰でも、自らの影という牢に閉じ込められた捕虜です。しかしそこから抜け出すことは可能なのかもしれない。そのような絶望と希望を描いたのが、『戦場のメリークリスマス』(英: Merry Christmas, Mr. Lawrence) であり、L・ヴァン・デル・ポスト『影の獄にて』(英: The Seed and the Sower, 種子と蒔く者 )なのです。
今回は心理学用語における「影」について詳しく説明しませんでした。理解補助としては、ユングの孫弟子である河合隼雄『影の現象学』がおすすめです。
『戦場のメリークリスマス』は現時点ではAmazonプライムビデオで無料で観れるので、昔観たという方も、まだ観ていないという方も、ぜひ観てみてください。
私としては原作もセットで勧めたいですが、現在は絶版になっているようで、古本で購入するしかないようです。全力で名作であると断言できるので、より多くの方の目に触れるように、どこかの出版社が、文庫で再販してくれればなあと思います。
→2023年12月、復刊ドットコム×書泉により、待望の復刻を果たしました(文庫ではありません)!!再び絶版になる前にぜひ読んでください。
以上、映画『戦場のメリークリスマス』の解説でした。
参考文献
[1] L・ヴァン・デル・ポスト『影の獄にて』由良君美、富山太佳夫訳、思索社、1985年、267頁、訳者あとがきより