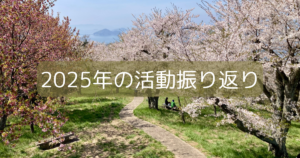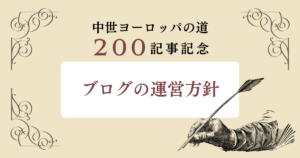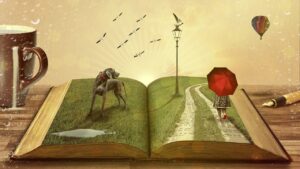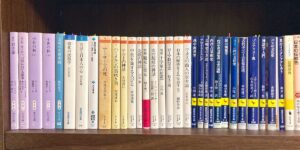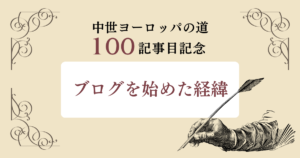昨年に引き続き、2024年も新しい取り組みを実施できた年でした。とくに、文学フリマへの初出店と、Twitter運用の強化は、大きな挑戦でした。本記事では2024年の出来事を振り返り、来年の目標を立てたいと思います。

記事内の写真はすべて、sousouが今年撮影したものだよ。写真も楽しんでね★
2024年に取り組んだこと
今年に新しく取り組んだことを3つ紹介します。
文学フリマへの初出店


今年、新しく取り組んだことの1つ目は、文学フリマに初めて出店したことです。5月に文学フリマ東京、7月に文学フリマ香川に出店しました。
印刷所に依頼して、同人誌を制作することも、自分の作品を販売することも初めてでした。印刷所から届いた何十部もの自分の本を見て、一度は冷静になり「こんなものが本当に売れるのか? 私はいったい何をしているのだ?」と思いました。しかしながら、結果的に多くの方のお手にとっていただき、本当に自信になりました。
また、活動を通じて友達ができたのも嬉しかったです。私は生まれたときからずっと首都圏に暮らしてきたので、これまでの人生で得た友達はほぼ首都圏に暮らしています。よって今年から暮らしはじめた、四国には一人も友達がいませんでした。しかし文学フリマ香川に出店することで、こちらに移住してきた、同年代の友達をつくることができました。


新しい取り組みをすると、視野が広がり、今まで着目してこなかった点に気づくことができます。今回、自分で本をつくり、販売したことで、本をめぐる経済や販売戦略に対する、知識を深めることができました。そのため、新しい挑戦をすると、何歳になっても学びがあることを、しみじみと実感しました。
古代ギリシア哲学者のソクラテスは、「自らが無知であることを知っている」という「無知の知」という概念を提唱しました。その言葉通り、本当に私たちは何も知りません。そもそも、人間の一生の間に、世界のあらゆる事象について知ることは不可能です。しかし、せめてできる限り多くを学び、善く生きようとすることが大切なのだろう、と思いました。
来年も文学フリマに出店することを予定しており、直近では2/9(日)の文学フリマ広島に出店します。その際には、Boothでの通販も予定しています。
文学フリマの出店レポートや、学んだことは以下の記事を参照ください。




Twitter運用の強化


今年、新しく取り組んだことの2つ目は、Twitter運用の強化です。(誰かの参考になればよいな、と思い非常にせきららに書いていますが、引かないでください……)
具体的には、本ブログをより多くの人に読んでいただくことを最終目標として、Twitterのフォロワー数を増やすことに注力しました。フォロワー数が増えることは、ブログ記事をTwitter内で共有した際に、より多くの方が訪問することに直結するからです。
結果として、フォロワー数は以下の通り遷移しました。それに比例して、ブログ記事も多くの方に読んでいただける結果となりました。
- 運用強化前のフォロワー数:約1000人(6月時点)
- 現在のフォロワー数:約5500人(12月時点)



長くお付き合いさせていただいている方も、今年からフォローしてくださった方も、本当にありがとうございます (*ˊᵕˋ*)
運用を強化したことで、得た知見もたくさんあります。そのなかで一番の学びだったのは、「長い文章を人が嫌う」ということです。長い文章とは、ブログ記事のような、通して読むのに10分ほどかかる文章のことです。
Twitter運用に最も力を入れていた時期には、1投稿の最大文字数である、140字に収まる歴史文化ウンチクを、毎日ひとつ発信していました。これらのウンチクのほとんどは、すでにブログで公開している内容の要約や抜粋です。よって、私としては、すでにブログ記事上で読まれている、使い古されたネタだと思っていました。
しかしながら、それらのウンチクに大きな反響をいただくということは、いいねの数だけ、ブログ記事を読んでいない人がいる、ということだと気づきました(※)。
※読んだうえで、応援をこめて反応くださる方もいらっしゃいます。いつもありがとうございます (* ᴗ ᴗ)⁾⁾
人はもともと、楽な手段を好む生き物です。加えて、情報の流れる速度が速い現代においては、腰をすえて何かを読む行為を、人びとが特に避ける傾向にあるのだと学びました。実際に、ブログ記事のリンクを貼った投稿と、同じ内容をウンチクとしてまとめた投稿を比較すると、後者のほうが数倍、ときには数百倍の反響があります。


いまはYouTubeやTikTokなどの、動画(それもできるだけ短い動画)が流行る時代なので、ブログは時代遅れなんだろうな、と思っています。しかし、私が好きなのは文章を書くことですし、読者の皆さんにも、文章を読む力をつけて、ブログよりもさらに読解力が要求される、本を読んでいただきたいと考えています。
だから、長い文章が嫌われる時代だとしても、読まれる文章や、発信の仕方を自分なりに模索していきたいです。お休みさせていただいている、Twitterのウンチク発信については、余裕ができたらまた再開したいです。
ブログのサイトデザインを刷新


今年、新しく取り組んだことの3つ目は、ブログのサイトデザインを刷新したことです。
本ブログはもともと、はてなブログサービスを使用して運営していました。しかし昨年の9月から、Wordpress上で独自運営しています。その際に、サイトデザインがパッケージになっている、TCDの”MAG” というサイトテーマを購入しました。
ところが、運用しているなかで不便な点が目立ち、「選ぶテーマを間違えた!」と思うようになりました。そこで今年の10月に、新しいサイトテーマを購入することにしました。



サイトテーマはけっこうお高くて、1万円~2万円くらいの値段幅だよ。なので事前調べはしっかりしよう!泣
とはいえ、自分でデザインを組み立てる手間ひま・Wordpressのバージョンアップのたびに行う運用の手間ひまを考えれば、驚くほどお安いよ。sousouは買うときに、「サブスクリプション型ではなく、買い切り型なんだ⁉」とびっくりしたよ。
人気のサイトテーマを比較検討した結果、国内シェアがNo.1の、”Swell(スウェル)”というテーマを買うことにしました。日本人の方が開発者で、痒い所に手が届く、素晴らしいテーマです。私はとくに以下の点で、他のテーマより気に入りました。
- 記事のアクセス数に応じた「人気記事」の一覧を自動で出力してくれる
- ホーム画面を、ブログ型ではなくサイト型にカスタマイズできる
- ユーザーが感覚的に操作しやすいデザイン。個人的にはとくに、ヘッダーの「西洋史を学ぶ」「物語をつくる」などの大カテゴリにカーソルをあわせると、子カテゴリが一覧で出てくる点を気に入っている。
- 豊富なデザインパーツが備わっている。つまり追加機能(プラグイン)を入れる必要がない。プラグインは余計な容量を食うし、セキュリティ面でリスクが上がるため、なるべく入れないほうがよい。
Swellの公式サイトは以下です。デザイン例を紹介した、デモサイトも複数あるので、ブログのサイトデザインに悩んでいる方はぜひ検討ください。




新しいデザインテーマを適用するにあたり、Swellの強みをきちんと活かしたいと思ったため、記事が属する分類(カテゴリ)の見直しも行いました。目的の記事を、読者の皆さんが探しやすくなることを第一に考えました。
熟慮の結果、「西洋史を学ぶ」「物語をつくる」「運営者の生活」の3つの大カテゴリをつくりました。また、1記事に対し複数のカテゴリを結びつける運用を廃止し、1記事に対し1つのカテゴリのみを結びつける運用にしました。そのほうが読み手に分かりやすいからです。
新しいカテゴリをつくったあとは、既存の記事(当時は全186記事)を分類しなおしました。かなり大変で、一日がかりでした。しかしそのかいあって、読者の皆さんが興味に応じて、目的の記事を探しやすくなったと思います。以下が刷新当時のお知らせで、多くの反響をいただき、頑張ってよかった~と思いました。
「中世ヨーロッパの道」のサイト大リニューアルを行いました!
— sousou | 中世ヨーロッパの道 (@sou_sou55) November 1, 2024
最も大きな変更点は、目的の記事が探しやすくなったことです。具体的には、以下3つの大カテゴリに、全186記事を分類しなおしました。他にも便利な機能が増えましたので、お時間あるときにのぞいてみてください♪https://t.co/TuRyzCQUpQ pic.twitter.com/OScjR12xrL
サイト全体のデザイン刷新に加えて、各記事の更新についても、現在進行形で取り組んでいます。具体的には、以下の点を意識して改善を行っています。
- 目を引くアイキャッチ画像
- 読みたくなるようなタイトル、導入文
- 文章にハイライトなどの装飾をつけて可読性を高めること
- 本文の内容が不足している場合には内容の追記
2024年の試練
ここからは、今年おきた試練を2つ紹介します。
ブログ記事が盗用される


今年おきた試練の1つ目は、ブログ記事の内容を盗用されたことです。
気づいたのは7月です。今まで検索エンジンで上位に出ていた記事が、まったくでてこなくなったため、おかしいと思って調査してみると、自分の記事内容を、そのまま70%くらい盛り込んだ記事が上位にあることに気づきました。
Googleの検索エンジンの仕組みでは、同じような内容の記事が2つある場合、どちらかがパクリだと判定されて、パクリ記事が検索圏外に追いやられます。つまりこの場合だと、私のオリジナル記事のほうが、パクリだと判定されてペナルティを受けたことになります。



なんだってー⁉ ぷんぷん!
対象の記事は、とある法人が管理しているサイトに属する、フリーライターが書いた記事でした。盗用の事例について調べてみると、どうやらライターの間では、すでに検索エンジンで上位にある、既存の記事内容を取り入れることは常識のようです。なぜなら、その記事を踏まえた上で、自分の記事にそれ以上の充実した内容を書かないと、検索順位で勝つことができないからです。
ただし、著作権の盗用になってしまっては、依頼主(今回は法人)に記事を納品できません。そのため、納品前にコピペ判定ツールにかけて、他の記事との一致率を30%以下にしなければなりません。もし30%を超えてしまったら、言い回しを替えたり、内容を減らしたり、逆に新しく内容を盛り込んだりして、内容を差別化する必要があります。
そこで私も、対象の記事を、コピペ判定ツールにかけてみました。すると一致率が28%で、30%に収まるぎりぎりを攻められていることが分かりました。つまり、言い回しは巧妙に変えられているのです。
しかし、文章の内容・構成・展開のすべてが、「自分が書いたんだっけ?」と思うくらい似ています。そして内容について、自分の記事は文献を3つほど参照していて、出典も記載しているのですが、盗用疑いの記事は、出典をまったく記載していませんでした。つまりネットで情報を集めた可能性が高いです。


腹を立てた私は、サイトを運営している会社に、盗用疑惑を指摘することにしました。ただし、相手が納得する証拠を出さなければ、訴えをかわされてしまいます。そこでまずは、説得材料を準備しました。
具体的には、2つの記事内容の対応表をつくり、(言い回しは異なるものの)一文一文の主旨が同じであることを示しました。また、記事の公開日について、自分が先であることを示すために、該当記事の公開をお知らせした、Twitterの投稿を用意しました。



じつは、ブログの画面上で見えている記事の公開日は、簡単に変更できてしまうらしいんだ(データベース上は変更できないと思うけど、サーバー会社が管理しているから、自分は見れないよ)。
だから、記事の公開日を示すために、該当の記事リンクを貼ったTwitterの投稿を用意したんだよ。Twitterの投稿には日付が入っているからね。
そうして運営会社に問い合わせてみると、その日のうちに返信があり、盗用を認めた上で、対象の記事を削除してくださいました。盗用疑惑の記事を見つけたときには、ものすごく腹が立ったけれど、結果としては、よい社会勉強になりました。
それ以降は、盗用されうることを想定して対策しているので、次に同じことが起きても、もっと武装して対応できると思います。(盗用されないのが一番だけどね!)
Twitter運用によるストレス


今年おきた試練の2つ目は、Twitter運用によるストレスです。
先述した通り、ブログをより多くの人に読んでいただくことを目標として、今年はTwitterのフォロワー数を増やすことに注力してきました。そのため、投稿が多くの方の目に触れることは、基本的にとても嬉しいです! しかし投稿が注目されると、それに比例して、心ない人からの投稿叩きが多くなり、疲れてしまいました。
投稿叩きの分類でいうと、以下が多いです。(前提として、投稿主への敬意にかけた文面)
- 否定:「この内容は間違っている」「こういう考えはよくない」など
- 知識マウント:「私はこうだと思うけどね」
- あげあし取り:投稿の主旨でない部分を拾って、「この内容は間違っている」など
- 単なる悪口。ただし、多方面にできる限り配慮した文面にするように意識してからは、悪口は少ない。
ようは、投稿叩きをする人は、その投稿が注目されていることが「気に入らない」のだと思います。気に入らないから、否定したり、もっと詳細な知識をかぶせたりするのだと思います。(あくまで想像の域ですが……)
私はこのような人たちに対しては、「モンスタークレーマー」を受け流すときと同じ態度をとっています。つまり、とにかく刺激しない・関わらないのが一番なので、全部無視します。しかしながら、ストレスなものはストレスなので、できることなら、このような内容は一切見たくないです。
とはいえ、応援してくださっている方の期待に応えたい、ブログをより多くの方に読んでいただきたい、という気持ちもあるので、Twitterの運用はつづけていきたいです。そのため、ストレスのかかりにくい、かつ無理のない運用の仕方を模索中です。



フォロワーの多さに比例して、こういうストレスが増えるだろうから、インフルエンサーや芸能人さんは、メンタルが激つよなんだろうなあ。すごいや……!
2024年にできなかったこと
歴史文化系の記事をあまり書けなかった


今年は時間に余裕ができたので、「歴史文化系の記事をたくさん書くぞ!」と意気込んでいました。
しかしながら、今年書いた歴史文化系の記事、すなわち「西洋史を学ぶ」に分類される記事の総数は12本でした。個人的には、予想していたよりも書けなかったという感覚です。平均すると、1カ月に1本書いていますが、目玉カテゴリの記事更新が月いちの頻度では、すこし寂しいです。
このブログの場合には、月に4回くらい、一週間に1回くらいの頻度で新記事を投稿できるのが理想だと思っています(※)。今年書いた記事の総数としては、本記事を含めて60本でした。平均すると月に5本も書いており、全体としては思ったより多いなと驚いています。



頑張った!!
来年は数よりは記事の種類に重きを置いて、「西洋史を学ぶ」カテゴリを月に平均2本書くことを目標にしたいです。
SEO的には、ブログは更新頻度が高ければ高いほど、高評価になり、検索エンジンで上位になります。ゆえに、ブログ運営の指南本では、たいてい一日1本か、二日に1本の頻度で記事を更新することが理想とされています。
しかし質の悪い記事を書いては元も子もないので、ブログの内容によって、適切な更新タイミングを考えることが大切です。
本ブログの目玉である、歴史文化カテゴリの記事は、何かしらの本を1冊~複数冊参照しているため、アイディアを思いついてから完成させるまでに、短くとも1週間は必要です。よって他の分類の記事もあわせて、月4回の更新頻度が精いっぱいかなと思います。
理想の理想でいえば、「毎週○曜日に更新!」というリズムをつくり、読者の皆さんに「○曜日=ブログ更新の日だ!」と思っていただけるようにしたいです。
小説をあまり書けなかった


昨年は、月に一本の短編小説を書く取り組みをしていました。その結果、14編の短編が溜まったため、文学フリマで短編集を販売できたというわけです。
しかしながら、今年はブログ記事の充足に力を入れていたため、ほとんど短編を書けませんでした。よって、文学フリマで短編集の新刊をしばらく出せそうにありません。



『おとぎ話集Ⅰ』を販売したから、『おとぎ話集Ⅱ』も販売したいと、sousouは思っているよ。
小説執筆の時間がなかった、というより、頭の切り替えが難しかったから、ブログ記事ばかり書いていたのだと思います。ブログ記事も小説も、文章を書くという行為では同じです。しかしながら、頭の使い方が全く異なり、書くべき文体も異なります。よって、ブログ執筆の休憩がてら小説を執筆する、という行為が難しいのです(※)。
※その証拠に、小説をたくさん執筆した昨年は、ブログ記事ではなく小説ばかり書いていた。
ブログ記事を一本書くと決めたら、完成するまではその頭の使い方・文体でいたほうが楽で、逆もしかりです。来年はブログ記事も書きたいけれど、小説も書きたいので、うまい頭の切り替えを模索しなければならないな、と思っています。週の前半と後半で期間をわけて、前半は小説、後半はブログ、という風に切り替えるとか……?



まあ、とにかく楽しければ何でもいいね★
2024年の私生活での変化


最後に、2024年の私生活の変化にも触れたいと思います。最も大きな変化は、春に、首都圏から四国に移住したことでした。
「四国に住みたい!」と場所特定で考えていたわけではなく、子供の頃から自然に囲まれた暮らしに憧れていて、いろんな縁が重なった結果、四国になりました。
都会で生まれ育った人が地方に移り住むと、さまざまなギャップが生じ失敗することも多いと聞きます。しかし私の場合は、この1年間、とても快適に暮らせています。
以前の記事(本さえあれば何もいらない)でも書きましたが、最近は本当に物欲がなくなったので、都会に比べて商品の品ぞろえが悪い田舎でも満足しています。そもそも、オシャレをして出かけるような場所がほぼないので、物が壊れたり服が破れたりしない限りは、何もいりません……。


そのため今のところは、移住してよかったと、心から思っています。高い建物が少ないので、毎日、山から太陽が昇るようす、山に太陽が沈んでいくようすを見られます。電車は混んでいないし、ご当地ニュースがのんびりしているし、人が機械的でなく、あたたかいです。



昨日も、服を取りに行ったクリーニング屋のお姉さんと、あたたかいやり取りをしたよ。
何より、人口密度が低いので、田園地帯や、浜辺などの広い空間を独り占めできます。都会では家を出た瞬間に見知らぬ人が視界に入り、どこへ行っても常に視界に人がいるので、空間を独り占めできるのは本当に贅沢です。
私の苗字は、関東では珍しいため、これまでの人生では、同じ苗字の世帯に1組しか出会ったことがありませんでした。しかし父の故郷であるこちらに移り住みはじめてから、同じ苗字の人がたくさんいて、「まるで故郷みたいだ!」と感動しています。
2025年に注力したいこと


2025年に注力したいことは以下の通りです。
- 「西洋史を学ぶ」カテゴリの記事を増やす。
- 小説を定期的に書く方法を模索し、執筆の習慣をつける。
小説の執筆について、長編にも挑戦したいと思っています。短編について、試しに何本か書いてコツを掴んだあとは、すらすら書けるようになったので、長編についても、コツを掴めば書けるような気がします(気がします…)。
短編には短編の面白さがあるけれど、長編には長編の面白さがあるので、どちらも書けるようになって、表現の幅を広げたいです。



書きたい物語の内容に応じて、短編にするか長編にするか、選べるようになれたら楽しいと思うんだ。
おわりに
今回は、2024年の振り返りと、来年の目標の整理を行いました。
今年は以下のことを中心として、さまざまな新しいことに挑戦できた一年でした。
- 文学フリマへの初出店
- Twitter運用の強化
- ブログのサイトデザインを刷新
来年も健康を第一に、興味のおもむくままに様々なことをしてみたいと思っています。まずは、年明け2/9(日)に開催される、文学フリマ広島が楽しみです。初めて画集を販売します!
今年も1年ありがとうございました。皆さまにおかれましても、よいお年をお過ごしくださいませ。



よいお年を~!