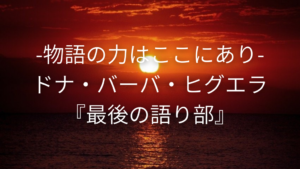はじめに
前回は『星の王子さま』だけではないサン=テグジュペリにて、サン=テグジュペリ作品の魅力を紹介した。今回は、彼の飛行士としての経験を元に書いた小説のうち、『人間の土地』を読んで印象に残ったエピソードの所感を3点、綴ろうと思う。
自由を得た奴隷はその後どうなるのか
印象に残ったエピソードとして第一に、奴隷解放のエピソードをあげる。
サン=テグジュペリによる、郵便会社での勤務経験を元に書いた小説には、さまざまな飛行場が登場する。そのなかの一つに、現モロッコの西部に位置するカップ・ジュビーという飛行場がある。その飛行場に駐在しているフランス人たちは、現地民であるモール人(またの呼び名をムーア人)との交流があったそうだ(※)。
※サン=テグジュペリ(フランス国籍)が郵便機で世界を飛び回っていた時代、アフリカはその大部分をイギリスとフランスに支配されていた。そのため彼はフランスの支配に屈しないモール人たちのことを、作中でしばしば「不帰順族」と呼ぶ。
飛行場員と交流があったモール人たちは、それぞれの奴隷を連れていた。奴隷たちはみな「バーク」という名で呼ばれていたが、その中で一人、「ぼく」の印象に残った「バーク」がいた。「ぼく」が曰く、通常、奴隷となった人びとはその身分を受け入れ、主人の喜びを自分の喜びとするようになる。しかしそのバークだけは違った。彼は奴隷商人に捕まる前の、家畜追いとしての過去を忘れなかった。そのバークは、「ぼく」が知る限り、奴隷という運命に抵抗しつづけた最初の一人だった。
バークは、奴隷の身分に安住しなかった、人がよく、待ちくたびれて平凡な幸福に安住するようには。
サン=テグジュペリ『人間の土地』堀口大學訳、新潮文庫、平成31年、140頁。
「ぼく」は、在仏の友人たちの協力も得て、バークをモール人から買うことに成功した。彼を故郷に返すためだ。そうしてバークは自由になった。しかし、長年待ち望んでいたはずの自由を、老バークは、ほろ苦く感じた。というのも、カップ・ジュビーを去り、アガディールに辿りついたバークは、世間がいかに自分と無関係かということに気づかされたからだ。
アラビア人の屋台店の売り子も、往来の通行人も、皆が彼のうちなる自由な人間を尊重し、平等に太陽を分かちはしたものの、ただそれだけで、だれ一人、自分には彼が必要だと知らせたものはなかった。彼は自由だった。だがあまりにも無制限に自由なので、自分の重量を地上にまるで感じないほどだった。彼には、気ままな歩行を妨げる人間相互関係の制圧が欠けていた。彼には、人が、何にもあれある行動をしようとすると、必ず付随しておこる、あの涙が、別れの悲しさが、譴責が、よろこびが欠けていた。彼にはつまり、彼を他の人間たちに結びつけ、彼を重厚にするあの無数の関連が欠けていた。
同上、150-151頁。
私はこのエピソードを読んで、解放された奴隷が幸せになるとは限らない、ということに気づかされた。そして、『グラディエーター』という映画を思い出した。その映画の舞台は五賢帝時代のローマで、主人公はマキシマスという名の将軍だ。彼は皇帝の策略で妻と子供を殺され、自らも奴隷商人に囚われの身となる。
だが、マキシマスはその境遇から自由になりたいとは思わない。自由になっても、もはや彼の家族はいないからだ。彼の目的はただ一つ、妻と子供を殺した皇帝に復讐することだ。自由を手に入れた奴隷が、必ずしも幸福ではないということは、この映画によっても意識させられる。(名作なのでぜひ観てね)
私はバークのエピソードを、現代日本社会に当てはめてみた。「社畜」という言葉が存在する通り、私たちは一種の会社奴隷である。定年後のサラリーマンが燃え尽き症候群となる要因の一つに、それまで仕事一筋で人生を過ごしてきたから、という要因があるだろう。このエピソードが私たちにもたらす教訓は、決して会社の奴隷になってはならないということだ。
たしかに生きるためには働かなければならない。しかし会社と私たちの関係はしょせん、ギブアンドテイクの契約関係だ。私たちが身を粉にして働く義理は全くない。生きがいは仕事以外にたくさんあったほうがいいし、人間関係も仕事以外でたくさん持っていたほうがいい。そうしないと私たちは、仕事がなくなったとき、降ってわいた自由に直面して、バークのように途方に暮れてしまうだろう。
宇宙的な力を持つ少女の運命
印象に残ったエピソードとして第二に、少女特有の不思議な力を書いたエピソードをあげる。
「ぼく」はある日、アルゼンチンのコンコルディアという場所で、野原に着陸する。そこで「ぼく」は穏やかな夫婦に拾われ、彼らの家に一晩泊めてもらうことになる。彼らはいかにも平凡な夫婦だったが、その家についた途端、彼はおとぎ話を生きるような体験をする。
ところが、道を曲がると、とたんに、月かげを浴びて、林が一つ現れた。そしてその木立ちのうしろにこの家が。なんとこれは不思議な家だろう。ずんぐりしていて、頑丈で、まるでお城みたいだ。この伝説の中のシャトーは、ポーチをくぐるといきなり、僧院ほども平和な、確実な、落ち着いた仮の宿を提供しているらしく思われた。
そこへ二人の娘が現れた。彼女たちは禁断の王国に立つ二人の裁判官のように、厳格な目つきで、ぼくを見据えるのであった。
同上、93頁
娘たちは食事中、「ぼく」を横目で見張りながら、突然現れた来訪者に用心深く評価を下そうとしていた。そしてときには、試金石として「ぼく」に言葉を投げかけ、その返答の仕方を値踏みしていた。彼を彼女たちの愛育の動物の一つに加えたものかどうかと。
しかし「ぼく」は、彼女たちはその後、他者を判定する宇宙的な力を失ってしまっただろう、と嘆きながら振り返る。それは彼が思うに、彼女たちがある一人の男性に夢中になる運命だからだ。そのとき娘たちは女となり、王女から奴隷へと降格する。
あの二人のフェアリーは、その後どうなったことだろう? たぶん、結婚したであろう。(中略)雑草や蛇を相手の彼女たちの友情はどうなったことだろう? あのころの彼女たちは、何か宇宙的なあらゆるものに関与していたのであったのに。ところが、やがて一日、娘の中に女が目覚めるのだ。(中略)そして天然の花園のような自分の心までも彼に与えてしまう。人工的な手入れの行きとどいた花園だけしか愛しえない彼に。こんなことで、そのばか者が、王女様を、奴隷にして連れていってしまうというようなわけあいになる。
同上、102頁
私はこのエピソードを読んで、たしかに少女には、大人の女性にはない、なにか超自然的な力があると思った。少女に大人にはない力が備わっていることは、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』を思い浮かべると分かりやすいだろう。
不思議の国へと迷い込んだアリスは(あるいは夢の中の出来事だったのかもしれないが)、現実では起こりえない、へんてこな出来事にすぐ適応する。例えばアリスは、身体が大きくなったり小さくなったりする食べ物の存在を受け入れ、煙草をふかす青虫の存在を受け入れ、現れたり消えたりする猫の存在を受け入れ、なにより動物たちが人語を話すことを受け入れる。
最近読んだ、ロード・ダンセイニの『魔法使いの弟子』にもそのような少女が登場した。ミランドラという名の彼女はラモン・アロンソという名の主人公の妹で、瞳に嵐のような激しさを持っている。
(前略)塔の主とラモン・アロンソの二人がまるで気づかないことが、そこにひとつあったのである。ほっそりとしたこの少女が、どんな大金を入れた持参金箱も比べものにならないほどの輝きを、その眼に宿しているということ、である。少女の輝きは、黄金よりもさらに恐ろしく、愛らしかった。金をもとめる男たちをあざけり、男たちの策略を笑いものにし、男たちの妄想をくつがえし、男たちの夢に灰をかぶせる、そんな輝きだった。
ロード・ダンセイニ『魔法使いの弟子』 荒俣宏訳、ちくま文庫、2003年、 22頁。
ミランドラには、サン=テグジュペリが恐れつつも心惹かれた、少女特有の宇宙的な力が備わっている。しかしそれの力は、誰かに恋することによって、彼女が気づかないうちに失われてしまうのかもしれない。
自分の命が危機にさらされたときに思うこと
印象に残ったエピソードとして最後に、不時着して生死を彷徨う人びとのエピソードをあげる。
『人間の土地』では、当時の郵便飛行の危険性が読み取れる話がしばしば取り上げられる。代表的なエピソードとしてまず、アンデス山脈に不時着し、氷点下40度の寒気のなかから、5日と4晩歩いて帰還した「ぼく」の僚友ギヨメの話がある。次に、これが本物語のメインパートだが、砂漠に不時着し、喉の渇きと幻覚と幻聴にさいなまされながら帰還した、「ぼく」と機関士のプレヴォーの話がある。
本記事ではギヨメの話を中心に取り上げよう。当然だが、ギヨメは一睡もせずに歩きつづけた。雪山のなかで一度横になったら最後、そのまま永遠に目覚めることができないからだ。ギヨメは自分の帰りを待っているはずの仲間と妻のために歩きつづける。しかし一度、雪の中にはらばいに倒れたとき、起き上がるのを諦めようとした。そのとき彼は、自分が死んだあと、妻に支払われる保険金のことを考えた。失踪の場合、法律上の死の認定は4年後になる。その間、妻はどうやって生活を立ち行かせるのか?
ギヨメは再び立ち上がり、歩きだした。何度も意識を失いながら、仲間と妻が待っている下界に向かって。サン=テグジュペリは、このように人が遭難しているとき、真の遭難者は当事者ではなく、帰りを待っている人びとなのだと語る。
難破者は、ぼくらを待っている人々だ! ぼくらの沈黙に、脅かされている人々だ。すでに恐るべき過誤によって、悲嘆にくれている人々だ。ぼくらは、彼らに向かって駆け出さずにはいられない。ギヨメも、アンデスの遭難から帰還したとき、ぼくに語った。彼は難破者に向かって駆けつけたのだと。これは世界的の真実だ。
サン=テグジュペリ『人間の土地』堀口大學訳、新潮文庫、平成31年、202頁。
救いは一歩踏み出すことだ。さてもう一歩。そしてこの同じ一歩を繰り返すことだけ……
同上、61頁。
私は命が危険にさらされた経験はないが、「苦しいときに、一歩を踏み出すことだけ考える」という部分に非常に共感した。私は学生時代のうち数年間、長距離種目を専門として陸上競技をやっていた。長距離走は孤独なスポーツだ。自分の周りに他の選手がいるときはまだよいのだが、そうではない場合も多々ある。一人きりでただ、自分の脚を腕を動かすことだけ、少しでも速くゴールにたどり着くことだけを考える。
ギヨメのエピソードを読んで、私は自分の命が危険にさらされたとき、走っているときと同じような気持ちになるのだろうか、と考えた。しかし明確に異なるのは、頑張る理由だ。長距離走を頑張る理由は、自分のプライドがかかっているからだ。つまり自分がライバルに勝つためだ。しかし遭難しているときに頑張る理由は、自分を待っている誰かのためだ。つまり大切な人が悲しむのを防ぐためだ。
どちらがより頑張れるかといえば、後者だろう。自分のプライドと大切な人の笑顔を比べれば、より守りたいのは、大切な人の笑顔だ。ギヨメも、最初から自分の命のことなど気にしていなかった。ただ、自分の帰りを待っている人のことを想って、絶望的な状況でも歩きだしたのだ。
おわりに
今回はサン=テグジュペリ『人間の土地』を読んで印象に残ったエピソード3点と、その所感を綴った。『夜間飛行』もとてもよい小説なのだが、考えさせられることが多かったのは、『人間の土地』のほうだった。
ちなみに私は今でも長距離を走る。しかし今ではライバルに勝つために走っているのではないし、自分(の記録)に勝つために走っているのでもない。究極的には楽しいからだろうか。走っているときには苦しくて苦しくて、マラソン大会等に申し込んだことを後悔するのだが、ゴールしたときの達成感が好きだ。苦しいときはいつも、「一歩前へ……一歩前へ……」と考えている(正確には腕を振れば脚は勝手に前へ出るので、「腕を振って」だ)。それを繰り返しつづければ、いつかは終わることが分かっているから。
以上、『人間の土地』を読んで考えたことであった。