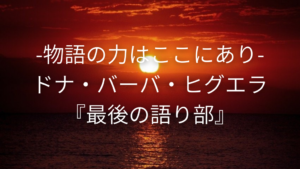はじめに
ロード・ダンセイニの『エルフランドの王女』と出会えたのは本当に幸運だった。
2021年7月現在、『エルフランドの王女』は絶版になっている。ところがある日、行きつけの本屋へ行くと、新品の『エルフランドの王女』が陳列されていた。それが陳列されていた本棚は、本屋へ行くときには必ず確認することにしている、海外文学の棚だった。つまり『エルフランドの王女』は、以前からそこに陳列されていたはずで、私はそれを何度も見ているはずなのに、そのときにはじめて、そこに存在することに気づいたのだった。
ダンセイニの名前は以前から知っており、幻想文学好きな人に人気らしい、ということまでぼんやり知っていた。ただ幻想文学にもいろいろとジャンルがあるし、果たして私の好みに合うだろうか?とそれまで慎重な態度を取っていた。しかし『エルフランドの王女』を手にしたとき、題名にある「エルフランド」をダンセイニはどう書いているのだろう?と非常に興味を引かれた。
「エルフランド」はその名の通り、妖精が暮らす地だ。「エルフランド」のような「異界」は非常に古くからある概念で、前近代の人びとは、人間が暮らさない場所には、超自然的な存在が暮らしていると考えてきた。超自然的な存在が暮らしている代表的な場所は森で、これについては以前西洋における森の歴史で紹介した。こうして私は、「異界」に対する興味から、ダンセイニの小説をはじめて購入することに決めたのだった。
今回は、ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』を考察する。ネタバレがややあるので、未読の方はそれを了承の上読んでいただきたい。ただし肝心の結末は本記事では述べない。
物語のあらすじ
物語のはじまりは典型のうちの典型といっていいほどありきたりだ。
アールの郷の評定衆はある日、国王の前にまかりでた。そして、今の世は新しいことがなく退屈であるため、魔法を使う国主にアールを治めてもらいたいと望んだ。国王はその望みを聞き入れ、自身の長男アルヴェリックに、エルフランド(妖精の国)の王の娘と結婚するよう命ずる。そうすればアルヴェリックの子供は妖精の血を引くことになり、将来的に魔法を使える王が誕生することになるからだ。こうしてアルヴェリックは、エルフランドの王女を娶るために、はるか彼方にあるエルフランドを目ざして旅立つ。
つまり物語は、美女との婚姻を目的にした青年による、冒険から始まる。神話や昔話における伝統的なロマンス物語のプロットを踏襲しており、個人的には非常に好感をもった。そして冒頭を読んだ時点で、この物語のクライマックスは美しい妖精の娘との結婚であり、それまでにさまざまな苦難(例えばドラゴンと闘うとか)が待ち構えているのだろう……と想像した。それが伝統的なロマンス物語のプロットだからだ。
しかし、その想定はいい意味で裏切られることになった。アルヴェリックの冒険には多少の苦難が伴うが、予想以上にあっけなく終わる。エルフランドの王女リラゼルはアルヴェリックを一目見て恋に落ち、父が引き留める前にエルフランドを去りましょう、と彼を急かす。なぜなら妖精の王の魔法は、エルフランド内でしか機能しないからだ。つまり妖精の王が魔法を使う前に、二人が境界を越えて人間の住む土地まで逃げきれば、二人は誰にもに邪魔されずに結婚することができる。そして、間一髪のところでアルヴェリックとリラゼルの冒険は成功した。
ここまでの話が『エルフランドの王女』を構成する34章のうち、たった4章までの話だ。え?このあとどうするの???と真剣に思った。アルヴェリックの冒険の目的は4章までで達成されている。ダンセイニは残り30章で何を語るというのか。
結論をいうと、物語の主題はここから移る。ようは、4章までは結婚が目的だったのだが、それ以降は結婚後の問題に焦点が移る。数多くの物語で繰り返し語られているように、人間と超自然的な存在の結婚生活には困難が伴う。『鶴の恩返し』の鶴は正体がばれるや夫の元を去るし、『メリュジーヌ物語』のメリュジーヌも正体がばれるや夫の元を去る(※)。アルヴェリックとリラゼルの場合、問題となったのはキリスト教への信仰心だった。
※『メリュジーヌ物語』概要を参照。
『エルフランドの王女』の世界観では、人びとはキリスト教を信仰している。そのため、アルヴェリックはリラゼルに信仰をすすめる。しかし「妖精」であるリラゼルは当然、キリスト教を受け入れることができない。妖精自身が、キリスト教と相反する概念だからだ(※)。リラゼルはそれでも、夫への愛ゆえにキリスト教の教えに従おうと努力するが、徐々にアルヴェリックとのすれ違いが多くなっていく。我慢できなくなったリラゼルはついに、父の元、つまり故郷のエルフランドへと帰ってしまう。そこから、アルヴェリックと彼の息子(リラゼルの息子でもある)が、リラゼルを人間界へ連れ戻すための冒険が始まる。
※妖精がキリスト教で受け入れられない理由は、イギリスにおける魔法の歴史を参照。
おとぎ話の伝統の踏襲
『エルフランドの王女』を読んでまず印象的だったのが、おとぎ話(民話あるいは昔話ともいう)の伝統をきちんと踏襲しているところだ。前章ではその一例として、「美女との婚姻を目的に冒険にでかける青年」というテーマを紹介した。これはとても古くからある物語のテーマで、例えば『竹取物語』にも同じテーマが使われている(美女がかぐや姫で、冒険にでかける男性が彼女への求婚者)。
作中でおとぎ話の伝統を踏襲している箇所として、他に2つの例を紹介したい。
『エルフランドの王女』がおとぎ話の伝統を踏襲している例として1つ目に、人間界と異界における時間の流れの差を挙げる。アルヴェリックがリラゼルに求婚するためにエルフランドに入り、たった1日を過ごしている間に、人間の世界では10年以上が経っていた。アルヴェリックがアールの城へ戻ってくると、父はすでに死去し、顔馴じみの護衛兵や召使たちは以前よりずっと年を取っていた。つまり、人間界とエルフランドでは時間の流れが異なるのだ。
異界で短い時間を過ごしている間に、人間界ではずっと長い時間が過ぎている、という現象はおとぎ話では典型だ。例えば日本の昔話には『浦島太郎』があり、アイルランドの昔話には『オシーン Oisín』がある。

『オシーン』を知らない方のために、内容を簡単に紹介する。
オシーンという名の青年は、ニアヴという名の妖精の王女と出会い、結婚してティル・ナ・ノーグ(常若の国)という妖精の国で3年間暮らした。そのうちオシーンは故郷が恋しくなってきたため、ニアヴに一時的に故郷に帰りたい旨を伝える。ニアヴは戻らないほうがいいと反対したが、オシーンがどうしてもと譲らないため、旅の足として白馬を用意する。そして彼女は「故郷へ戻っても、決して馬から降りてその地に足をつけないように」と忠告する。
こうしてオシーンは故郷へ戻ってきた。しかし彼は、故郷が以前とはまったく様子を変えていることに驚く。そのうち彼は、重い岩をどかそうと奮闘している人に出会い、力に自信があったために助けてあげることにする。ところが重い岩をあげたとき、馬の腹帯が切れて彼は落馬し、故郷の地に足をつけてしまった。するとたちまち、オシーンは老人に変わり果てて息絶えた。なんと、オシーンがティル・ナ・ノーグで3年過ごしていた間に、人間界では300年の時が過ぎていたのだ。ニアヴが与えた馬は、『浦島太郎』の玉手箱と同様に、絶縁体の役割があったといえる。
『エルフランドの王女』の世界観も、例に挙げた2つのおとぎ話のように、人間界では時の流れが速く、異界では時の流れが遅い、という点が共通である。この点で『エルフランドの王女』はおとぎ話の伝統を踏襲していると言える。
*
『エルフランドの王女』がおとぎ話の伝統を踏襲している例として2つ目に、「3」という数字に重きを置いていることを挙げる。妖精の王女リラゼルの父は、それぞれ1回しか唱えることができない、「三つの強力な呪文」を持っている。そのうちの1つは、リラゼルを人間界からエルフランドへ連れ戻すために使われる。
ユング心理学の研究者として知られる河合隼雄は、『昔話と日本人の心』や『昔話の深層 ユング心理学とグリム童話』にて、昔話では「3」という数字がよく使用されることを、繰り返し述べている。例えばグリム童話の題目を一覧すると、「三年寝太郎」「糸くり三人女」など、3の数字が使われる題目が圧倒的に多いことが分かる。
この象徴的意味については、正反合の図式に基づいて、対立するものの統合ということがまず考えられ、キリスト教の三位一体の象徴と結びついて、ますます精神的な統一を表すことが強調された。これに対して、ユングは夢内容の分析を通じて、無意識から産出される象徴としては、むしろ四が完全統一を表すことが多く、三はそれに到る前の力動的な状態を反映していると主張した。
河合隼雄『昔話の深層 ユング心理学とグリム童話』講談社、2019年、110頁。
日本の昔話でいえば、『三枚のお札』が3という数字が使われる話の典型である。このように、おとぎ話でよく使われる「3」という数字を魔法の鍵としている部分に、『エルフランドの王女』がおとぎ話を踏襲している点が見受けられるのである。
生と不死
次に、『エルフランドの王女』の内容を踏まえて、生と不死の関係について考えたい。
エルフランドでは基本的に、時間の流れが存在しない。エルフランドの王が時を止めているからだ。ただし、彼の精神エネルギーが何か新しいことに出会い、動くとき、エルフランド時はほんの少しだけ動くことになる。それ以外の場合は、その地は永遠に時が止まったまま、静寂に包まれることになる。
私はエルフランドでは、時間は全くたたない、と書いた。何か出来事が起こるとしたら、それは時がある証拠であり、もし時がなければ、どんな出来事も起こりはしない。これがエルフランドでの時間だった。蜜のように甘い空気に夢まどろむ永遠の美の中で、動くことや変化すること、また新しいことなどを求めるものは一切なく、ただ、かつてあったすべての美を、永遠に沈黙したまま観想している恍惚があるだけだった。その恍惚は、はじめて呪文や歌によってつくりだされた時と同じように強烈に、いつも魔の芝生の上に輝いた。
ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』原葵訳、沖積舎、2018年、64頁。
エルフランドに暮らす王と王女リラゼルは、時の流れの配下におかれないため、永遠に生きることになる。つまり彼らは不死ということだ。
私は不死について考えるとき、そこには矛盾が含まれているのではないかと考える。不死(ときに不老不死)とは、上記で紹介したエルフランドのように、変化しない状態のことだ。一方で、生きるとは、常に変化しつづけることだ。発芽した植物はやがて花を咲かせて枯れるし、生まれた子羊はやがて母羊となりやがて死ぬ。生物の細胞は絶えず活動しており、それが内面的にも外面的にも生き物に変化をもたらす。
「不死」は「死なず」という意味だが、「死なない」ことは変化が止まっている状態である。すなわち、生きる=変化しつづけると定義する場合には、「不死」は「死」と同義である。だから私は、童話や物語に出てくる「不死」や「不老不死」の生き物たち(エルフや魔女)は、永遠に生き続けるようにみえて、実は永遠に死んでいることと同じなのではないかと思う。実際、何の変化もない人生を生きるとしたら、果たして私たちは自身が「生きている」と感じるだろうか?
不老不死について、上記からさらに考察した記事がこちら:物語における不老不死をめぐる考察
エルフランドとは何か
最後に、『エルフランドの王女』における「エルフランド」が象徴しているものを考えたい。
エルフランドはアールの郷の東から南にかけて存在する。しかし人びとは決して、その方角には目を向けようとしない。なぜなら、魔の国はあまりにも魅力的な要素を備えており、その国の魅力に一度とらえられてしまうと、畑をたがやしたり家畜を世話したりといった、生きていくためにしなければならない仕事がおろそかになってしまうからだ。だから彼らは、まるでエルフランドがこの世に存在しないかのようにふるまう。アルヴェリックや彼の息子のオリオンがエルフランドについて尋ねても、彼らはとぼけ顔をして何も応えないのである。
アルヴェリックがリラゼルを連れ戻すため、エルフランドを訪ねると宣言したとき、共に旅をする者として名乗りをあげたのは、たったの5名だった。彼らはそれぞれ、月に憑かれて気がふれた男、うすのろ、恋わずらいの男、羊飼いの若者、それに詩人だった。最初、アルヴェリックは羊飼いに露営の長を任せていたが(というのも旅の仲間のうちでは彼がいちばんまともに思えたので)、それはうまくいかなかった。そこでアルヴェリックは、うすのろの若者に露営の長を命じた。といのも、「このような旅では、いちばんえらいものは、正気ではなくて狂気だということがわかった」(138頁)からだった。
このエピソードから、エルフランドを目指す者は、狂気を帯びている必要があることが分かる。つまり、日常世界に属しきっている者にはエルフランドは見つけられず、そこから逸脱している者がエルフランドを見つけることができるのだ。
狂気の重要性は、芸術家に変人が多いことを考えると分かりやすいだろう(※)。狂気は既存の世界に新しい風をもたらす点で、人類のより良い生活のためになくてはならないものである。山口昌男は『道化の民俗学』のなかで以下の通り、ミハイル・バフチンのカーニヴァルにおける狂気の考察を引用している。
※ちなみにダンセイニは旅の仲間のなかに「詩人」を入れているが、「詩人」は西洋の中世期には魔術師とみなされることがあった。理由は西洋中世期における言葉と文字に宿る霊性を参照。この点でも「詩人」が浮世離れしていることが分かる。
狂気のテーマは極めて重要である。(中略)狂気はもちろん、アンビヴァレントなものである。それは一方では道徳的低下と破壊(今日これらの側面だけがネガティブに協調させすぎるのだが)の側面を持つが、他方それは再生と真なるものの至現という積極的要素を含む。狂気は、智慧の反対物であり、さかさまの智慧、さかさまの真実である。
山口昌男『道化の民俗学』岩波現代文庫、2017年、48頁
以上より、エルフランドは日常世界から逸脱した者だけが関われるものだということが分かる。すなわちエルフランドが象徴するのは「日常世界からの逸脱」だ。しかし、それだけではないところがこの物語の深いところだ。エルフランドはそれに加えて、「若さ」や「純粋さ」をも象徴している。
アルヴェリックの息子であるオリオンは、妖精の血を半分引いている。これによってアールの郷には、トロールや鬼火など、さまざまな魔法がもたらされることになった。物語の冒頭でアールの郷の評定衆は、王が国に魔法をもたらすことを望んだが、晴れてその望みが叶ったのである。
ところが、今は年老いた評定衆は、魔法がもたらされることを快く思わなくなっていた。そこで彼らは、昔からアールに暮らしている知者、魔女のジルーンデレルに助けを求めた。今やアールにはエルフランドの魔法が多くもたらされすぎているので、それを追い払ってほしいと。しかし魔女のジルーンデレルは、その懇願をきっぱりと断って言う。
「帰るがよい、お前がたの村へ帰るのだ。若い時分には魔法を望んでいたが、お前がたぐらいの年になると、もはやそれを要らぬという、そういうお前がたは年から来る心の盲(めしい)だ、眼が盲いているよりもっと真っ暗闇で、その中では見ることも知ることも、どうあがいても感知することすらできぬ、そういう暗黒をつくる心の盲(めしい)だ。その暗黒から発せられるいかなる声も、魔法に対してわたしに魔術を行わせるようにすることなど、できはせぬ、帰れ!」
ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』原葵訳、沖積舎、2018年、286頁
上記のジルーンデレルの言葉より、エルフランドが「日常世界からの逸脱」だけではなく、「若さ」と「純粋さ」も象徴していることが分かる。子供の頃は誰しも新しい変化を望む柔軟な心があるはずなのに、年老いた人間は新しい変化を忌み嫌うようになる。エルフランドの存在は、そのような人間の性を風刺しているようにも思える。
おわりに
今回はロード・ダンセイニの『エルフランドの王女』について考察した。
まず、本作品がおとぎ話の伝統を踏襲していることを説明した。その根拠として、以下の3点をあげた。
- 主人公が美女との婚姻を目的に冒険にでかけること
- 人間界と異界における時間の流れの差
- 「3」という数字へのこだわり
次に、本作品の内容を踏まえて生と不死の関係について考察した。生きることを、常に変化しつづける状態であると定義する場合、「不死」や「不老不死」は変化しないために、死んでいる状態と同じである。よってエルフランドの住人は「不死」でありながらすでに死んでいるといえる。
最後に、エルフランドが象徴するものを考えた。エルフランドは第一に、「日常からの逸脱」を象徴している。その根拠として、エルフランドを探し求める旅の仲間がみなどこか非日常性を帯びており、露営の長を務める者が、仲間うちで最も狂気を帯びていることをあげた。
エルフランドは第二に、「若さ」と「純真さ」を象徴している。その根拠として、魔女ジルーンデレルの台詞を引用した。若者だった頃は国に魔法がもたらされることを望んだ評定衆が、年老いた頃に実際に魔法がもたらされると、それを嫌がるという主旨の台詞だ。そのため、エルフランドは年老いるに従い変化を嫌う人間の性を風刺しているともいえる。
全体的な感想をいうと、本物語はファンタジー小説として良くできており、個人的にはとても気に入った。ファンタジー小説はピンキリで、考察のしがいがある本格的な物語は「ファンタジー」と分類される物語のなかで非常に少ないのだが、『エルフランドの王女』はその数少ない本格的な物語の部類に入る。純文学が好きな人にも、安心してすすめられる良作である。
本物語を読んだことがきっかけで、ダンセイニの他作品も読んでみたいと思い、『魔法使いの弟子』も読んでみた。こちらも非常に良かったので、興味がある人はぜひ読んでいただきたい。
以上、ロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』の考察だった。