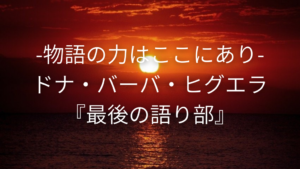はじめに
今回は『アルジャーノンに花束を』を読み、解釈したことをまとめます。ネタバレありです。
あらすじ
物語は、知的障害者であるチャーリイが知能レベルを高める手術を受けるところから始まる。手術は今まで動物に対してのみ実施されてきた。そのため、チャーリイが人間として初めての被験者となった。チャーリイは手術後、同様の手術を受けたねずみのアルジャーノンと競いながら、知能を高めていく。
手術は身体的な害を及ぼさなかったが、精神的な害を及ぼした。具体的には、知能レベルが急上昇した「私」は、「チャーリイ」と別人格になった。「チャーリイ」は特に、女性と関わる際に「私」の邪魔をしてくるようだ。
ある日、自分の知能に関する研究を進めるなかで、一般人の知能を遥かに凌駕した「私」は、アルジャーノンと「私」が辿る運命を知った。「人為的に誘発された知能は、その増大量に比例する速度で低下する」。つまり「私」は、手術で得た知能が元通りに低下することを知ったのだ。
物語を読み解くカギ:意識と無意識
『アルジャーノンに花束を』を読み解くカギは、心理学における「意識」と「無意識」です。「意識」は覚醒している心の状態、「無意識」は自分では意識できない心の状態を表します。人間が意識できる心の動きはよく氷山の一角にたとえられ、ほとんどの心の動きは無意識のなかにあると言われています。無意識は潜在意識とも言われます。
無意識の領域にある心の動きは、夢に現れます。心理学者は患者の夢を分析することによって、患者が無意識に抱えるトラウマなどを明らかにします。『アルジャーノンに花束を』の作中で、「私」も夢に出てきたことを記録します。
チャーリイ・ゴードンと2人の女性
ここから、チャーリイ・ゴードンという主人公を、「私」と「チャーリイ」に分けて説明します。「チャーリイ」とは、手術前から主人公に存在する、知的障害者としての人格です。「私」とは、手術によって「チャーリイ」に新たに生まれた、天才としての人格です。
手術の後「私」は、「チャーリイ」の意識の領域を支配し、「チャーリイ」を無意識の領域に追いやりました。しかし「チャーリイ」も自分の一部であるため、「私」は彼がときどき無意識の領域から自分を見ているのを感じます。
とくに「私」が女性と愛を交わそうとする際、チャーリイは「窓の向こうの闇」や「戸口」から「私」を見つめます。そのせいで「私」はいつも女性とうまくいきません。しかし、「なんらかの理由でチャーリイはアリスを恐れているがフェイを恐れていない」のです。なぜ女性によって「チャーリイ」の感情が変わるのか、それを考えていきます。
アリス=「私」
「チャーリイ」がアリスを恐れるのは、彼女が「私」と同じ性質をもつ人間だからです。
「私」とアリスは、秩序を求めるという共通点があります。
アリスは几帳面で、何もかもをきちんと整頓しなければ気が済まない性格をもちます。以下はアリスの部の描写です。
何もかもがきちんと整頓されている。出窓には磁器の人形が一列に並んでいて、みんな同じほうを向いている。ソファのクッションは、むぞうさに投げ出されているのではなく、ソファをおおっている透明なビニールのおおいの上に同じ間隔をおいて並べてある。
ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』小尾芙佐訳、早川書房、2019年、171-172頁。
一方「私」も同様に、何もかもをきちんと整頓していなければ気が済まない性質をもちます。以下はフェイが「私」の部屋をはじめて訪れた場面です。
「ひゃあ!こんなにきれいに片づいている部屋って見たことない。独りもんの男がこんなにきちんとしているなんて考えられる?」
「いつもこうというわけじゃないけど」と私は言いわけをした。「ここへ越してきたときのままですよ。ここにきたとききちんと片づいていたから、ずっとこうしておかなくちゃいけないような気がしてね。いまじゃ、何もかもがちょっとでも動いていると気になるんですよ」
同上、255-256頁。
アリスが「私」と同じ性質であること、つまり鏡あわせの分身であることは、以下の文章からも現れています。先ほどと同じく、「私」がアリスの部屋について描写する場面です。
ソファの向かいの壁には、凝った細工の額縁に入ったピカソの<母子像>の複製がかかっている。その真向かい、つまりソファの上の壁には、ルネッサンス時代の仮面をつけ剣を持った伊達姿の廷臣が、薔薇色の頬をした怯える乙女を護っている絵がかかっている。部屋全体が、ちぐはぐな感じがする。まるでアリスは、自分が何者なのか、どんな世界に住みたいと思っているのか、きめかねているというようであった。
同上、172頁。
外見上の秩序を求めるのみで、「自分が何者なのか、どんな世界に住みたいと思っているのか決めかねている」。この一文に関してはこれ以上語られず、著者がなぜアリスにこのような性質をもたせたのか、疑問が残ります。
わたしは著者がこの一文で、「私」の鏡であるアリスを通して「私」の性質を表したかったのだと考えました。急激に知能をつけた「私」もまた、情緒面ではその成長が追い付いておらず、精神的な欠陥を抱えています。知識としては色んなことを知っている、でも自分が何者なのか、何をしたいのかが分からない。それが「私」なのです。
そして、著者は高い知能だけをもち、「チャーリイ」のもつ純真さやあたたかい心を失った「私」を、アリスの言葉を通して揶揄しています。これは著者が、物語を通じて読者に知ってほしかったこと、つまりこの物語のテーマであると感じます。
「高いIQをもつよりももっと大事なことがあるのよ」
同上、433頁。
フェイ=「チャーリイ」
アリスと「私」は秩序を求める人間です。音楽や映画など、高尚で上品な趣味を好みます。一方で、フェイと「チャーリイ」は無秩序(混沌)を求める人間です。そして両者ともダンスを好みます。「チャーリイ」がフェイを恐れないのは、彼女が自分と同じ性質をもつ人間だからです。
以下はフェイの部屋の様子です。アリスや「私」の部屋の部屋とは正反対の、混沌とした部屋として描写されています。
室内はごったがえしていた。折りたたみ式の小卓が何十となくあり、そのすべてにはねじまげた絵具チューブが占領しており、チューブの大半は縮んだ蛇のようにかたく干からびていたが、あるものは生きていて、色とりどりのリボンを吐きだしている。
(中略)
床には靴だの脱いだストッキングだの下着だのがほうりだしてあって、さながら彼女は歩きながら服を脱ぎ、脱いだものを歩きながらほうりだしていく習慣があるかのようだった。ほこりがうっすらといたるところにつもっている。
同上、261頁。
一方で、「チャーリイ」も混沌とした部屋を好みます。以下の場面では、「私」の知能が低下し、「チャーリイ」が意識の領域にのぼってきています。それはチャーリイ・ゴードンの一人称が「ぼく」となっていることから分かります。
彼女(アリス)は部屋をいつもきれいにしておいてくれ、ぼくのものを片づけたり皿を洗ったり床を磨いていたりしている。けさみたいに彼女をどなったりしてはいけない、泣かせたりしたくなかったのに、泣かせてしまったから。でも彼女はこわれたレコードや破いた楽譜や本をかきあつめて、きちんと箱に詰めこんだりしてはいけなかったのだ。それでぼくはかっとしたのだ。ああいうものにはなにも手を触れてもらいたくない。ああいうものはそこに積みあげておきたいのだ。
同上、428-429頁。
以前は何もかもがきちんとしていなければ気が済まなかった「私」でしたが、このころには無秩序(混沌)を好むようになってきています。無秩序を好むのは「チャーリイ」の性質です。チャーリイ・ゴードンの意識の所有者は「私」から「チャーリイ」に変わろうとしています。
フェイと「チャーリイ」の共通点は、その性格にも表れています。
アリスはチャーリイ・ゴードンに付きまとうフェイという女を嫌いになれませんでした。むしろ好意すら抱いています。フェイについて、アリスは以下のように言います。
「彼女って何かがあるわ」と帰りの車内でアリスは言った。「なんだかわからないけど。率直さとか、打ち解けた信頼とか、自己中心的でないこととか……」
私は同意した。
同上、342頁。
なぜアリスはフェイに好意を抱いたのでしょうか。それはフェイが「チャーリイ」と同じように、人を引き付ける「何か」を持っているからです。「何か」は作中ではあえて説明されません。なぜならフェイと「チャーリイ」は無秩序であることが魅力だからです。
以下は、アリスが「チャーリイ」が持っていた性格を、「私」に説明する場面です。
「本気で言っているのよ。以前のあなたには何かがあった。よくわからないけど……暖かさ、率直さ、思いやり、そのためにみんながあなたを好きになって、あなたをそばにおきたいという気になる、そんな何か。それが今は、あなたの知性と教養のおかげで、すっかり変わって――」
同上、190-191頁。
要約すると、「私」がフェイと愛を交わすことに成功し、アリスとはうまくいかないのは、「私」の分身である「チャーリイ」が、フェイ(=「チャーリー」)を恐れず、アリス(=「私」)を恐れているからです。
「私」はどこへ?
チャーリイ・ゴードンの意識の領域は、最終的に「チャーリイ」に支配されてしまったのでしょうか。知能レベルの向上により生まれた「私」は、知能レベルが元に戻ると同時に、消滅したのでしょうか。そうだすると、「私」がどこへ行ってしまったのかという疑問が残ります。
結論から言うと、「私」が消えたのでも、「チャーリイ」が意識を支配したのでもありません。「私」と「チャーリイ」が同化した人格が、チャーリイ・ゴードンになったと考えています。
「私」と「チャーリイ」が同化したと読み取れる箇所を3つ紹介します。
1.「チャーリイ」が「私」に手をさしのべる
以下は、「私」が酒に酔ったとき、トイレの鏡に「チャーリイ」を見る場面です。
「……おれはおまえの敵さ。おれはね、おれの知能をあっさりあきらめるつもりはないぞ。あの洞窟に戻るわけにはいかないんだ。おれ、行くところがないんだよ、チャーリイ。だからおまえにどいてもらいたい。おまえは、おまえのいるべき場所に、おれの無意識の中でおとなしくしていろ、そしておれをつけまわすのはやめろ。おれはあきらめないぞ――だれがなんと思おうが。いかに孤独であろうが。彼らがくれたものを護って、世界のため、おまえたちのような人たちのために、貢献したいんだ」
ドアのほうを向いたとき、彼が手をさしのべたように見えた。なんとばかばかしい。私はただ酔っぱらっていて、あれは鏡の中の私の映像なのだ。
同上、368頁。
「チャーリイ」は誰とでも友達になれる人です。以前は怖がっていた「私」に、手を差し伸べるということは、「私」の存在を認め、「私」と友達になりたがっていると解釈できます。
2.アリスと愛を交わすことに成功する
「私」はフェイと愛を交わすことができても、アリスとはどうしてもできませんでした。「チャーリイ」がアリスを恐がっているからです。しかし知能の下降期に至り、ようやく想いを達成することができました。
何も言うすきもあたえず彼女は私にキスをした。そしてカウチの私のかたわらにすわって頭を私の胸にもたせかけるあいだ私は待っていた、でもパニックはおこらなかた。アリスは女だ、でもきっとチャーリイには、彼女が自分の母親でも妹でもないことがわかったのだろう。
同上、424頁。
先ほど、アリスが「私」と同じ性質をもつ「私」の分身であることを説明しました。アリスと恐がらないということは、「チャーリイ」はもはや「私」を恐がっていないということになります。そして合体という行為は、アリスと「私」だけでなく、「チャーリイ」と「私」の同化も暗示されているとも解釈できます。
3.「チャーリイ」の学習の動機が変化した
手術をする前、「チャーリイ」は①母親に捨てられたトラウマ(本人は気づいていない)と、②友達をつくりたいという想いから「かしこくなりたい」と思っていました。そのため、①母親と対面してトラウマを乗り越え、②知能レベルと友達ができるかどうかは関係ないと理解したあと、「チャーリイ」の学習の動機はなくなったはずです。しかし、「チャーリイ」は再び「りこーになりたい」と思い、学習意欲に燃えています。その動機は、「私」の記憶です。
やぶけた表紙の青い本を読んだときとてもいい気分だったのをちょっとおぼいている。
(中略)
そういうわけですからぼくわりこうになるようにがんばればまたああいう気ぶんになれるとおもう。いろんなことをしることやりこうになることわいいことです世界じうのことを全ぶしりたいとおもう。いますぐまたりこーになりたいな。すわって一日じう本が読めたらいいな。
同上、448頁。
「やぶけた表紙の青い本」とは、「私」が破いたミルトンの『失楽園』です。以前読んだ本の内容を思い出せなくなった「私」は、苛々して『失楽園』を破いてしまいました。「私」が『失楽園』を読んだとき、「チャーリイ」は無意識の中にいました。にもかかわらず、「チャーリイ」がそれを読んでいい気分になったことを覚えている、ということは、「私」の記憶が「チャーリイ」に取り込まれたということです。つまり、「私」と「チャーリイ」は同化し、もはや別々の人格ではなく1人のチャーリイ・ゴードンになったと解釈できます。
以上の3点から、チャーリイ・ゴードンの意識の領域を支配する人格は、「私」と「チャーリイ」が同化した人格であると考えられます。
おわりに
今回は『アルジャーノンに花束を』について個人的な解釈を述べました。まず、チャーリイ・ゴードンと、2人の女性の関係について考察しました。次に、物語の最後で「私」がどこへ行ったのかについて考察しました。